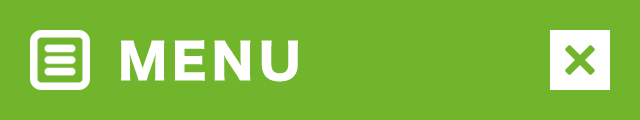死をことほぐ社会へ向けて
【第2回】
医療と介護・ケアの違い
……死のコントロールを目指す医療とコントロールしない介護・ケア

誰にもいずれ「死」は訪れる。多死社会を迎えた現在の日本において、いずれくる「死」をどのように考え、どのように受け止め、そして迎えるか。医療、介護・ケアの問題とあわせて、みなさんも一緒に考えてみませんか。

死のコントロールという視点
介護・ケアが提供される場所では、「死」が話題になる。「死」をどう遠ざけるか、どうコントロールするか。それに反して、「死」をどう受け止めるか、むしろ「死」をどう早めるかという議論もある。
「死」に対するものには、このような両極端がある。遠ざけたい、さらには不老不死を望むというものから、早く迎えに来てほしい、その先には安楽死や自殺を考えたり、実際にそうしたりする人もいる。しかし、どちらもなんだか狂っているという気がする。
死を避けることはできない。それが現実だ。いかに医療を受け続けても、いつかは限界が来る。医療ができることは「死」の「先送り」に過ぎない。それに対して、安楽死というのも、その先には必ず「死」が来るということはわかっているのだが、それをあえて自分から早めようとする。「死」の「前倒し」といえばいいのか。
この二つは一見真逆のように見えるが、実はとても良く似ている。どちらも「死」をコントロールしようとしている点では同じである。だから、死を遠ざけようと頑張る人が、その頑張りに疲れ果て、先送りが困難なうえに苦しいとなった時に、コントロールの方向を「先送り」から「前倒し」に変える。そんな場面にたびたび出会う。
「死を避ける社会」とは、「死をコントロールしようとする社会」でもある。それは「死を避ける社会」の反対にあると思われる「安楽死」にもつながっている。これに対する私の答えは明確である。「死をコントロールすることはできない」ということだ。もちろんある程度予測することはできる。しかしそれはあくまで確率の問題にすぎない。「肺炎になっていますが、抗生物質による治療をすれば1か月後の生存確率は40%から60%へと1.5倍になります」というものだ。しかし、個別に起こることは、医療を受けたとしても1か月後に死んでいる人もいるし、医療を受けずに生きている人もいる。さらに80歳の人であれば、30年後にはほとんど死亡する。これは確率の問題ではない。医療によるコントロールは必ず限界を迎える。そこで登場するのが安楽死や自殺である。
どこまでも医療に依存して死を避けようとすることと安楽死や自殺は、どちらも死をコントロールしようという点でとても似ているということが少しは説明できただろうか。さらに言えば、コントロールできない死を何とかコントロールしようとする世の中を基盤に持つという点で、この2つは似ているどころか、同じであるといってもいい。
死をコントロールしない介護・ケア
そこで考えたいのは、死をコントロールしないですむ世の中とはどんな世の中なのだろうか、ということである。その一つが、死ぬまで十分な介護・ケアを受けられる社会ではないだろうか。さらに医療も全く無力ではない。緩和ケアの十分な提供という役割がある。これらが提供されれば、安楽死を望む人もずいぶん減るのではないだろうか。
しかし、それでも安楽死や自殺を考える人はいるだろう。そうした人は「なんでもコントロールできる」、あるいは「できるならばコントロールしたい」という考えにとりつかれているのかもしれない。コントロールしようとしない方が幸せである、そんな場面をたくさん見てきた。原稿を書いていて、訪問診療に行っていたある人の一言がよみがえる。
娘が言う。「そんな寝てばっかりいると寝たきりになっちゃうよ」。それにこたえて本人が言う。「寝ているのが一番楽なんだよ。寝ている今が一番幸せなんだ」。食事は介助で食べさせてくれる。排泄の介助もしてくれる。着替えも手伝ってくれるし、風呂まで入れてくれる。痛いと言えば痛み止めもくれる。こんな幸せは今までなかったということだろうか。
コントロールしない幸せ、皆さんも一緒に考えてみてください。