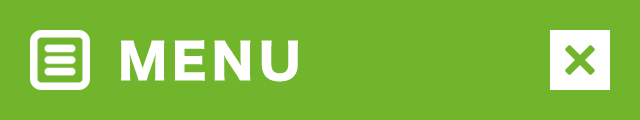死をことほぐ社会へ向けて
【第1回】
「死を避ける社会」と「現実には避けられない死」
……医療と介護・ケアの役割

誰にもいずれ「死」は訪れる。多死社会を迎えた現在の日本において、いずれくる「死」をどのように考え、どのように受け止め、そして迎えるか。医療、介護・ケアの問題とあわせて、みなさんも一緒に考えてみませんか。

連載開始にあたって
筆者は、特別養護老人ホームの配置医を主な仕事としている医師である。そこには日常的に「死」がある。しかし、それぞれの人にはそれぞれ一回きりの非日常の「死」がある。この二つの間には何か埋めがたいギャップがある。そのギャップについて、常日頃考えているのだが、その考えたことを、世に向けて、活字にして届けようというのが、こうして書き始めた背景である。まずは「死」についてのいろいろな対応について取り上げようと思っている。
「死を避ける社会」、それが今の世の中の王道である。医学の進歩がそれを実現してきた。そこには感動のドラマがある。死に面した患者が、医療によって救われる。医療のドラマはそんな話が多い。反対に医療で助けられないというドラマもあるが、その背景は、死は悲しい、なんとかして避けたい、ということの裏返しであったりする。死が肯定的にとらえられることは少ない。
有名人の死が報道されると、誰も死んでよかったとは言わない。悲しい、信じられない、早すぎる、そんなコメントばかりだ。ただ、「ゆっくりとお休みください」というコメントもある。死には「休んでもいいんですよ」といういい面も垣間見える。
そんな今の世の中から少し離れたところで、多くの人が80歳、90歳まで生きる世の中の「死」について、一度考えてみたい。死はとかく医療との関連で語られることが多いが、死にかかわる場面では、医療より介護・ケアの方がはるかに重要ではないか。介護・ケアの現場での現状を起点に、今とは違う、医療への依存から脱し、どんな介護・ケアがありうるのか。さらに医療において、「死を避ける」だけではない、どんな対応が可能なのか。そんなことを考えてみたい。
とりあえず、現実にどうすべきかではなく、荒唐無稽といわれようが、死を避け、長寿を目指すばかりの現実から離れて、考えることに集中したい。介護・ケアと医療のはざまに身を置いて、日々の仕事とは別に、考えることをとことん突き詰めて、介護・ケアの役割を中心に、今こうして「死」について書こうと思っている。
医療と介護・ケアの役割
そこでまず言いたいのは、「死を避ける社会」と「現実には避けられない死」に対する、医療と介護・ケアの役割についてである。医療は死を避ける方向で提供される。しかし、最終的に死を避けることはできない。この現実に対して、医療者側から発せられる言葉の一つに「もうできることはありません」というのがある。これをもう少し正確に言い直せば「医療として死を避けるためにできることはありません」ということに過ぎない。そこで医療以外で提供できることは何かと考えれば、「医療に縛られ、病院で苦しい生活を続けるよりは、介護・ケアにシフトして医療に依存しない生活ができますよ」ということでもある。ただ説明する医者が介護・ケアについてよく知らないために、「できることはありません」と言っているだけなのだ。
連載の初めにあたり、是非言っておきたい。医療は「できることはもうありません」というが、介護・ケアは決してそういうことを言わない。「どこまでもできることがありますよ。死ぬまでお付き合いしますよ」というのが介護・ケアである。釈迦に説法かもしれない。しかし自戒を込めて、自分自身に向けて明確になったことを明言することで、これからの連載を書いていきたい。よろしくお願いします。