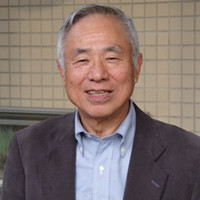石飛幸三医師の
特養で死ぬこと・看取ること
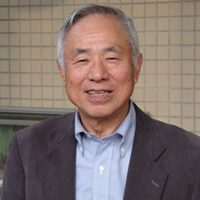
終末期の胃ろうなどの行きすぎた延命治療の是非について問題提起し、ベストセラーとなった『「平穏死」のすすめ』の著者が、特養での“看取り”を語り尽くします。
穏やかな最期を迎えるためにどうすればよいか? 職員と家族の関係はどうあるべきか? これからの特養の使命とは? 施設で働く介護、看護職に贈る「看取り」の医師からの熱いエール!
- プロフィール石飛 幸三(いしとび こうぞう)
-
特別養護老人ホーム・芦花ホーム常勤医。
1935年広島県生まれ。慶應義塾大学医学部卒業。1970年ドイツのフェルディナント・ザウアーブルッフ記念病院で血管外科医として勤務。帰国後、1972年東京都済生会中央病院勤務、1993年東京都済生会中央病院副院長を経て、2005年より現職。診療の傍ら、講演や執筆などを通して、老衰末期の看取りのあり方についての啓発に尽力している。
主な著書に『「平穏死」のすすめ 口から食べられなくなったらどうしますか』(講談社)、『「平穏死」という選択』(幻冬舎ルネッサンス新書)などがある。
第1回 血管外科医から特養の配置医へ
はじめまして。石飛幸三です。私は世田谷区にある芦花ホームという特別養護老人ホームで常勤の配置医[1] を勤めております。2010年に出版した『「平穏死」のすすめ-口から食べられなくなったらどうしますか』という本が思いがけずベストセラーとなり、今は全国各地の講演に呼ばれ、穏やかな最期、看取りのあり方について皆さまにお話させていただいております。
このたび、けあサポにて『特養で死ぬこと・看取ること』を連載することになりました。死ぬことを考えるのは国民全員の問題だと思っていますが、ここではとくに施設の職員の皆さまに向けて、人間らしい死にかたとはどういうものか、安らかな看取りを手伝うためにはどうするべきか、私の思うところを書かせていただこうと思います。
これまでのことを振り返る
今回は、自己紹介を兼ねて、少し昔話をさせていただきたいと思います。お付き合いいただければ幸いです。
血管外科医として
私は、消化器の胆道系の研究室にはじまり、ドイツ留学を経て、血管外科医となりました。ドイツからの帰国後、済生会中央病院に勤めまして、そこで、血管外科の技術を消化器外科に応用したり、動脈硬化の時代になってからは、動脈硬化とも戦いました。つまり、動脈硬化で痛んだ血管の修復・再生を受け持っていたのですね。
そこで33年、外科医として、「風邪でも切って治す男」と言われるほどの延命至上主義を貫いてきました。多くの命を救ってきましたし、済生会中央病院の外科を大きくしてきたプライドもありました。エリート医師としてチヤホヤされていましたしね。副院長という肩書きもあり、そのまま穏やかな時間が過ぎていれば、今頃はのほほんとリタイアしていたことでしょう。
転機が訪れる
それが、2つの出来事がきっかけとなって私の人生が変わりました。1つは病院との裁判です。詳細は省きますが、病院の不正を訴える裁判で、これが10年続きました。
もう1つは、私が70歳を迎える前に執刀した手術で患者さんが亡くなってしまったことです。患者さんは80歳にならんとするおじいさんで、脚の急性動脈閉塞でした。確実なのは、脚を切断する方法でしたが、本人は「歩けなければ生きている意味がない」とおっしゃり、方法があるなら治してほしいと訴えられましたので、それならばと、本人の意思を尊重したのです。できるだけの検査をして、血管造影検査で心臓や脳につながる血管の状態をしっかり調べて、これなら大丈夫ってことで数日後に手術を行いました。一刻の猶予もなかったのです。そうしたら手術の途中で心臓が止まってしまったのです。とにかくできるだけの処置をして、手術後はCCUで3日間頑張りましたが、結局亡くなってしまいました。ご家族は半狂乱で「命を返せ」と叫びました。それこそ訴えられそうな勢いでした。私は病院とも裁判をしていましたので、訴えられることが怖いわけじゃありませんが、このことは大きな十字架になっています。
老いに対して医療はどこまで介入するべきなのか、医療の意味とは…、家族の思い…そんなことを深く考えるきっかけになりました。
特養の配置医へ
これまで私は、「命を粗末にするんじゃない」と言って、手術をすすめてきました。患者を叱りとばしたこともあります。方法があるならやらなければいけない、と命の飛行機を飛ばし続けることしか考えてきませんでした。それらがすべて間違いだったとは思いませんが、しかし、医療にも限界があります。死なないということはありえず、誰しもが必ず死ぬわけです。今、私自身が老いを迎え、自分の死に方を考えるようになった時に、このままの医療のあり方で良いのか、と深く考えたわけです。
そんなことを考えているうちに、縁があって芦花ホームの配置医となり、そこで見た現実や感じたことをまとめたものが前述の『「平穏死」のすすめ』だったわけです。もちろん芦花ホームでの看取りが最初から素晴らしいものであったわけではありません。他の多くの特養と変わらず、言い方は悪いけど肺炎製造工場[2] のようなところでしたし、家族会との関係も険悪そのものでした。そんな芦花ホームが変わっていったきっかけがあったのです。
次回は、そのあたりのところからお話したいと思います。
―補足解説-
1. ^ 常勤の配置医・・・たいていの場合は外部の病院や診療所の医師が受託して担う。常勤の指定はないため、施設に医師がいないことが多く、常勤の配置医は珍しい。
2. ^ 肺炎製造工場・・・良かれと思って入所者にきちんと1500キロカロリー食べさせようとすることで、誤嚥を起こし、肺炎にしてしまい入院。入院先で胃ろうを作られて戻ってくるも、今度はその胃ろうが原因による誤嚥(流動食の逆流)によって肺炎になるという、負のスパイラルのことを皮肉った表現。