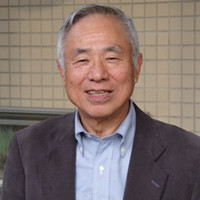石飛幸三医師の
特養で死ぬこと・看取ること
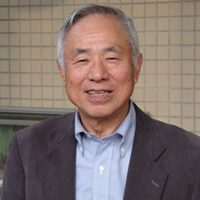
終末期の胃ろうなどの行きすぎた延命治療の是非について問題提起し、ベストセラーとなった『「平穏死」のすすめ』の著者が、特養での“看取り”を語り尽くします。
穏やかな最期を迎えるためにどうすればよいか? 職員と家族の関係はどうあるべきか? これからの特養の使命とは? 施設で働く介護、看護職に贈る「看取り」の医師からの熱いエール!
- プロフィール石飛 幸三(いしとび こうぞう)
-
特別養護老人ホーム・芦花ホーム常勤医。
1935年広島県生まれ。慶應義塾大学医学部卒業。1970年ドイツのフェルディナント・ザウアーブルッフ記念病院で血管外科医として勤務。帰国後、1972年東京都済生会中央病院勤務、1993年東京都済生会中央病院副院長を経て、2005年より現職。診療の傍ら、講演や執筆などを通して、老衰末期の看取りのあり方についての啓発に尽力している。
主な著書に『「平穏死」のすすめ 口から食べられなくなったらどうしますか』(講談社)、『「平穏死」という選択』(幻冬舎ルネッサンス新書)などがある。
第12回 特養の職員へのメッセージ
この連載はこの第12回でいったん区切りを迎えます。
特養での看取りをすすめ、穏やかな最期(死)を見つめてきた視点から、あれこれと書いてきましたが、最後に介護施設で働く職員のみなさんに私の思いを伝えたいと思います。
“おかしいこと”には一緒に声をあげよう!
私が書いてきたことについて、実は現場のみなさんは、すでに気がついていると思います。誤嚥性肺炎の製造工場になっている実態、胃ろうの実態、悲惨な終末期の実態等々、「このままでいいのか」「おかしいんじゃないか」、そう感じている方がたくさんいるのではないでしょうか。
もし、本人の望まない延命医療や不本意な最期へのやるせない気持ちや、穏やかな看取りを迎えさせてあげられない悔しさを感じている方がいるならば、ぜひ、声をあげてください。私自身、日本全国で講演をして、このことを伝えていますが、やはり現場のみなさんが直接声をあげて施設を変えていくことが何より重要だと思います。一緒に声をあげて、穏やかな看取りを実現できる施設をつくっていってほしいというのが私の願いです。
人間の生き方、死に方の伝え手に
看取りの場が在宅から病院へと移り、日本人の多くが、「死」や「死に方」を学ぶ機会が減ってきて、いざ、そうした事態に直面した時に、迷いのまっただ中に放り出されることになります。
けれども、みなさんは、施設の中で人間の生き方と死に方を学んでいます。それは、急性期病院での死とはかけ離れたものです。前回の介護士の言葉を再掲しますが、
「大切なのは死の瞬間だけではない。看取りは入所の時から始まっている。入所者がどうこれまで生きてきたのか、家族とここへきてどうかかわってきたか、それが最後に結実する」
こういう人間らしい生き方(死に方)を目の前で勉強させてもらっているわけです。それは、これから自分たちが歩む道でもあります。こうしたことをぜひ、伝え手として、死に方について不慣れで、迷い戸惑う家族に示していってほしいと思うのです。これは、みなさんならきっとできることですし、みなさんにしかできないことでしょう。
日本の未来を支えるみなさんへ
以上のようなことも踏まえて、これからの超高齢社会を本当の意味で支えていくのは、みなさんのような方々です。介護現場の最前線を支えるみなさんの肩にこの国の未来がかかっていると言っても過言ではないと思います。だから、しんどいことも沢山あると思いますが、負けずに頑張ってください。
私は、特養の配置医となって本当に良かったと思っています。ここへ来て、特養を支えるみなさんと出会えて本当によかった、もし、急性期病院にいたまま一生が終わっていたら、本当につまらない人生だったと思いますよ。
心底、心根のやさしいみなさんが、この先も大事な役割を果たし続けていけるように、社会や制度も変えていかないといけないと思っています。そのために私も微力ながら声をあげていくつもりです。
世界一の‘死の高齢化を迎えたわが国’は、‘人生途上のピンチを救う医療という人類の大事な使命’に加えて、‘老衰という自然の摂理を受容して人生の最期を支えるもう一つの大事な役割’の在り方を、今改めて示さなければならない時に来たのです。