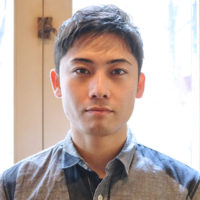介護職に就いた私の理由(わけ)
さまざまな事情で介護の仕事に就いた方々の人生経緯と、介護の仕事で体験したエピソードを紹介していきます。「介護の仕事に就くことで、こんなふうに人生が変わった」といった視点からご紹介することで、さまざまな経験を経た介護職が現場には必要であること、そして、それが大変意味のあることだということを、あらためて考えていただく機会としたいと考えています。
たとえば、「介護の仕事をするしかないか・・」などと消極的な気持ちでいる方がいたとしても、この連載で紹介される「介護の仕事にこそ自分を活かす術があった・・」というさまざまな事例を通して、「介護の仕事をやってみよう!」などと積極的に受け止める人が増えることを願っています。そのような介護の仕事の大変さ、面白さ、社会的意義を多くの方に理解していただけるインタビュー連載に取り組んでいきます。

花げし舎ホームページ:
http://hanagesisha.jimdo.com/
- プロフィール久田恵の主宰する編集プロダクション「花げし舎」チームが、各地で取材を進めていきます。
久田 恵(ひさだ めぐみ) -
北海道室蘭市生まれ。1990年『フイリッピーナを愛した男たち』(文藝春秋)で、第21回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。
著書に『ニッポン貧困最前線-ケースワーカーと呼ばれる人々』(文藝春秋・文庫)、『シクスティーズの日々』(朝日新聞社)など。現在、読売新聞「人生案内」の回答者、現在、産経新聞にてエッセイを連載中。
第56回 病院の看護師から介護の現場へ
自分らしい人生の最後をどう迎えるか、現場からの発信を続けています

醤野良子さん(66歳)
看護師&元ケアマネジャー
「自分の死を考える集い」(三鷹市)主宰
取材:久田 恵
倒れた夫に代わって大黒柱に
私が34歳のとき、39歳の夫が突然倒れたのです。
私は子育て真っ只中の専業主婦、下の息子がまだ3歳でした。夫は、父親の経営していた電気部品工場で働いていたのですが、仕事がなくなり、タクシーの仕事についていました。働き盛りの年齢と合わせて、神経を使う仕事でしたので、心配していた矢先のことでした。夜明けの洗車中に、クモ膜下出血に襲われたのです。手術で一命をとりとめましたが、この出来事が私のその後の人生の舵を大きく切らせることになりました。
私は、准看護婦の資格を持っていたので、すぐに生計の担い手になる覚悟を決め、病院で働き始めました。病気の夫と二人の子どもを抱えて無我夢中。どうやっていたのか記憶にないほどでしたが、幸いなことに1年半ほどで夫が仕事に復帰できるまでに回復し、あらためて、十年ぶりの医療現場を見回すゆとりができました。
延命治療至上主義
そこは、私には衝撃的な光景でした。
大量に投与される薬・抗生物質、高カロリー点滴。終末期の患者さんの止まりかけの心臓を、肋骨が折れるのも構わずに心臓マッサージをし、あげくに人工呼吸器を着ける・・・。そこは150床ほどの、大学病院からの下請け機能もある病院で、手術後、植物人間状態になった方の面倒を見続けるという事例もありました。今の医療は、「生活の生命」を看るのではなく、「医療の生命」を看る、延命治療至上主義にあることを思い知らされたのです。それは医療側だけの問題ではなく、患者側の問題でもある現実でした。
准看のままでは医者と治療に関しても、「死」について話すこともできないと思い、病院に4年ほど勤めた後、今の治療をもっと学ぼうと予備校に通い、看護学校に入学しました。
実は、私は青森県の出身で9歳のときに父親が家出したりして、母子家庭状態で育ったんですね。それで、高校へ行く代わりに国立の看護学校に入って准看護婦の資格を取りました。その後、東京の病院に勤めながら夜間高校に通いました。当時は、「静かな死」の看取りがまだありました。ただ、医療が大きく発展するうねりが来ている時代でした。
看護学校は3年で卒業しました。
准看時代に、看護の勉強を一度通過しているので、それに重ねて学んでいくことで、この学生時代は楽しかった。毎日のようにレポート、テスト、それに加えて子育てをしながらでしたが。もう夢中で過ごした時期でした。
卒業後、病院では、また悩むと思い、乳児院に勤めました。そこで出会ったのは、小さな身体に苦難の人生を背負った子どもたちでした。その子どもたちが3歳になって養護施設に移るまでに、排泄の自立だけはして送り出したいと、トイレットトレーニングを頑張りましたね。子育て経験のある人間は、そこでは私一人でしたので。
ケアマネジャーの資格は取ってから悩め!
そんなこんなで、夫の病気以来の人生は、怒涛のような日々で、疲れてしまったのでしょう。44歳のときに乳児院をやめて、人生の休暇のような日々を送りました。
その間に、当時、看護学生だった娘とインドに行き、マザー・テレサに会いました。インドでは、人の「生と死」のエネルギーを強烈に肌で感じる体験をして、忘れ得ぬ旅となりました。その体験が私の人生の次なるターニングポイントだったかと思います。
というのも、この休暇中に高齢者介護の施設長から声がかかり、私は介護の世界に足を踏み入れたのです。声をかけてくれた彼は、看護学校時代の福祉学の先生でした。彼から、「ケアマネジャーの資格を取る前には悩むな、取ってから悩め!」と言われて、ケアマネジャーの資格を取りました。
その施設長は、介護保険の始まった2000年の連休明けに心筋梗塞で、急逝してしまいました。そのときは、「老人を生かして44歳の施設長が死ぬ!!」と絶句してしまいました。
人の死は、いつ来るかわかりません。
そして、私は、看護師としてもケアマネとしても、「人の終末期」のことを常に考えざるを得なくなりました。そういう現場に生きていたからです。
静かに死なせてもらえない
あるとき、担当していた89歳の方が、気管支喘息の発作で入院したと聞いて、病室を訪ねました。人工呼吸器を着けた彼が、私に向かって、必死で「外せ、抜いてくれ」と手でチューブを引き抜くしぐさをしました。昼は家族が手を握っていても、夜にはベッド柵に手を縛られていました。そのため、状況が改善したとき、「一度外された人工呼吸器を次はつけない」と家族が断り、死を受け入れる決断をされました。
2週間後、彼は妻に看とられて息を引き取ったのですが、後日、家を訪問すると、奥さんから1枚の写真を見せられました。彼の鼻には、高栄養ミルクを注入するチューブが入れられていました。医療機関では、臨終間近な人にさえも、さまざまな治療法を講じるのです。今の日本では、静かに死なせてもらえないのです。
そういうことを実感してきました。
『幸せなご臨終』
10年ぐらい前です。私は、介護関係者を対象にした「寝たきり体験」の研修を受けたことがあります。紙おむつをして、体に装具をつけて寝ます。「点滴を外さないように、あなたもこうやって患者さんの手足を縛ったでしょう?」なんて言われて、ベッドの柵に手を縛り付けられました。息ははあはあ、心臓はバクバクしてパニックでした。さらに「喉が渇いたでしょう」と、吸い飲みを口の中にぐいぐい入れられました。寝たままで排尿するのも大変でした。さらに、栄養チューブ体験も。鼻から胃まで55センチもあって、オエッとなります、鼻から出ているチューブの先は高栄養ミルクに接続されていて、つばも呑み込めず、喉の違和感が苦痛で、苦痛で。その状態を延々続けるって、大変に苦しいことなのです。
現在、私がかかわる施設は、通所の介護施設で50人ほどが送迎バスで通ってきておられます。要介護度4や5という方もおられます。介護保険が始まったときは、胃ろうの方が多くて、3~4人の利用がありました。在宅で看ているけれど、家ではお風呂に入れないので、ということで通ってこられていたのです。
その通所施設で、「死について話す」機会があったとき、私は、はたと困りました。そのとき、中村仁医師の言ってくださっていたことを思い出して、勇気を持ちました。彼の出版された『幸せなご臨終』の本を読んで、どうしても会いたいと思った私は、彼が京都で主宰する「自分の死を考える集い」に参加するようになっていたのですが、彼がこんなふうに言っていたのです。
「人は、死について考えることを避けてはいけない。臆することなく話したほうがいい」、と。
「高齢者のみんなでこういう話ができる施設があっていい。医療でがんじがらめになって、死ぬに死ねない。そんな時代の中でどういう死を迎えたいか。それを自分の口で語れる。それができなくてはだめだ」と。
自分の死を考える集い
高齢の方には、「死ぬのはこわくないよ」と言う方が少なくありません。「延命は嫌だなあ」と言います。でも、具体的に延命ってどういうことなのかはよくわかっていません。身内の看取り体験がある方は、「チューブにつながれたああいうのは嫌。静かに死にたいね」、などとは言いますが。
中村先生とつながったことで私は、思い切って、地元で勉強会を始めてしまいました。そこに、在宅ターミナルをやっている先生を講師に招いたりして、この問題を発信し続けました。今も、地元で「自分の死を考える集い」を主宰しているのですが、この集いは、2か月に一度、いろんな方に講師できてもらって、体験や考えを話してもらいます。延べ51回、9年目になります。
在宅でどうしたら「静かな自分らしい死」を迎えられるか、それが私の一生のテーマなのです。

視力、聴力障害、片マヒ状態で研修。(チラシより抜粋)
- 【久田恵の眼】
- 日本人の80%が、病院で亡くなります。ほとんどの人が「家で静かに死にたい」と思っているのに、過剰医療でチューブにつながれて逝くのは、嫌だと思っているのに、その願いがかなえられることは稀でした。でも、今、高齢者の看取りはどうあるべきかが議論されるようになりました。醤野さんのように看護師としての専門知識をいかしつつ、介護現場で日々高齢者に寄り添って働いてきた方たちの切実な声が、私たちに届き始めているのです。