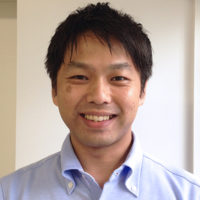介護職に就いた私の理由(わけ)
さまざまな事情で介護の仕事に就いた方々の人生経緯と、介護の仕事で体験したエピソードを紹介していきます。「介護の仕事に就くことで、こんなふうに人生が変わった」といった視点からご紹介することで、さまざまな経験を経た介護職が現場には必要であること、そして、それが大変意味のあることだということを、あらためて考えていただく機会としたいと考えています。
たとえば、「介護の仕事をするしかないか・・」などと消極的な気持ちでいる方がいたとしても、この連載で紹介される「介護の仕事にこそ自分を活かす術があった・・」というさまざまな事例を通して、「介護の仕事をやってみよう!」などと積極的に受け止める人が増えることを願っています。そのような介護の仕事の大変さ、面白さ、社会的意義を多くの方に理解していただけるインタビュー連載に取り組んでいきます。

花げし舎ホームページ:
http://hanagesisha.jimdo.com/
- プロフィール久田恵の主宰する編集プロダクション「花げし舎」チームが、各地で取材を進めていきます。
久田 恵(ひさだ めぐみ) -
北海道室蘭市生まれ。1990年『フイリッピーナを愛した男たち』(文藝春秋)で、第21回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。
著書に『ニッポン貧困最前線-ケースワーカーと呼ばれる人々』(文藝春秋・文庫)、『シクスティーズの日々』(朝日新聞社)など。現在、読売新聞「人生案内」の回答者、現在、産経新聞にてエッセイを連載中。
第51回 利用者とヘルパーはお互いさま。おかげさまの世界
「認知症」の人だろうが、「高齢」の人だろうが、誰もがみんな同じ

川俣由加里さん(55歳)
デイサービス(東京・杉並区)
介護職・介護カウンセラー・認知症管理指導士
取材:進藤美恵子
劇団天井桟敷
10代後半に家出をするまで、母と祖母と叔母の女系家族の中で育ちました。母は離婚した、いわゆる“出戻り”で、今のように「バツイチで~す!」と明るく言えるような時代ではなかったです。
看護師長(当時は看護婦長)としてバリバリの仕事人間だった母は、離婚したことを汚点と考え、自分を責め、自分で自分を傷つけていたと思う。だから世間に、後ろ指を刺されないようにという感じで私を育て……、育てたというよりも世間に顔向けできないという世間体を保つのに一生懸命でした。自分のプライドを守るのに必死だったんですね。看護師としては、最高の仕事をしていたと思います。
でも、母親業はできなかった。傷ついた自分をも許せない。だから人を許せない。そうなると、かわいいはずの我が子のちょっとしたことも許せずに、躾といえば厳しい躾ですけれども、温かい愛情を注ぐことはできなかった。母とは、「おはよう」、「行ってきます」、「ご飯美味しいね」というような当たり前の会話さえもない幼少時代でした。
そんな母との関係は窮屈で苦しいものでした。本当は寂しくてたまらなかったのだと思います。すごく苦しくてたまらないときに、寺山修司の著書「家出のすすめ」を読んだんです。友達に誘われて天井桟敷の芝居を観て、「私の居場所はココだ」と感じました。私は10代で家出をし、天井桟敷に入団しました。寺山修司の世界では、母親を何回も殺すんです。私の母親への怒りが芝居の中で浄化され、怒りをそこにぶつけられるということで、私は実際に母殺しをすることなく心が救われました。
子育てに介護にと、もう限界状態
劇団に入ったのは19歳のとき、1年ほどの演劇活動に没頭し、短大も卒業。24歳で結婚しました。私の幼少の頃からの夢は「温かい家庭」をつくることです。そして反面教師、自分の家庭を持ち、「子育てが始まったら決して、母親のようにはやらないぞ」と思っていました。
でも現実は、親から愛情を注がれたという感情の経験がないから、我が子にどう接していいのかわからなかったんです。子どもたちも少しずつ、いわゆる問題行動を起こすようになってきていました。子どもとの接し方に悩んでいる頃、今度はお姑さんが認知症になってしまった。未だ認知症という言葉も介護保険制度もない時代です。子どもが4歳と1歳のときに育児と平行して、姑の面倒をみることになったのです。
姑の介護が始まり心が息詰まった私は、キッチンドリンカーになりました。姑がウンチを食べる弄便をしたときはどうしたらいいのかわからなく、姑を殺してしまいたいと思うときもありました。今なら、介護のプロとして、「ご家族様だけでは無理ですから、プロの力を借りてください」って言えますけれども、その時に誰も私には手を差し伸べてくれなかった。夫の兄弟たちも「家をもらったのだから見るのが当たり前だろ」って感じで。私に対して労ってくれたり、味方をしたりしてくれる人がいなかったのです。
子育てに介護にと、もう限界状態でした。姑の介護をする私の姿を母の苦しそうな姿を見ていた4歳の息子が「いつも、おばあちゃん、おばあちゃんって、おばあちゃんのところに行くね」って言ったんです。まだまだ4歳。本当は自分だけをみて欲しい年代。息子も寂しかったのでしょう。息子にいっぱい我慢をさせました。
その後、姑が亡くなったときに印象的だったのは、ピンク色のかわいい顔をして亡くなったんです。そのとき小学1年生になっていた息子は、霊安室に脱帽して頭を下げて入り、「おばあちゃん、かわいい顔してるね」って。決して、気持ちよく介護できなかったのに姑はピンク色の顔をしていました。そのときに、「終わりよければすべてよし」かなって。私なりに頑張ったんだなって思えるようになって。でも、未だそこで介護の仕事に就こうとは思いませんでした。
心の便秘
子どもたちが思春期の頃は、いわゆる“問題児”と呼ばれるような、凄まじいものがいっぱいありました。小学校に行くようになると、学校に呼び出されて「一日中、子どもを見張っていなさい」と学校から言われることも。中学では、引きこもりになったり、非行したり……。「こんなに私が一生懸命やっているのに、なんで物ごとがうまく回らないんだろう」。子どもが悪い、親が悪い、お母さんが悪いと思っていた。そんなときにハッと気づくと、誰かの問題ではなく、自分自身の問題だとわかって。それからアダルトチルドレンのセミナーを受けて、結局は自分が自分を愛していない、自己否定をしているというところを気づきました。母親の未解決な感情を私も背負い、自分を許し愛せない。だから、頑張って認めてもらおうと何でも頑張ってきたのだと思います。
子どもたちの行動は、「母ちゃん、そんな生き方をしていて苦しくない?」といろいろメッセージを投げかけてくれました。家出したまま未解決だった私と母親との関係から、私との関係が苦しくなってきていた子どもからの問題提起だと気づいたのです。
それから心理学やスピリチュアル、精神学を勉強して、カウンセリングの資格を取得。同じように不登校や引きこもり、親子関係で悩む親御さんのカウンセリングを始めた。カウンセリングを始めることによって、何よりも私と子どもとの関係が一番見直されていきました。
カウンセラーになってもまだ、母を許せない気持ちが私自身を責め、苦しかったです。5年前に母ががんになり、私に対する攻撃が弱くなったときに、母との関係が変わってきました。母が大腸がんになったのも、「なって当然だ」と私は思いました。いろんな怒りとかを溜めて、結局、心の便秘。いろんな憎しみやなんだかんだと、溜め込んできたから、「がんになって、気づきなさいよ」というメッセージだと思って。私はある意味、母ががんになってよかったと思います。母のがんが私と母との距離を縮めてくれました。母のがんに私は、「ありがとう」と感謝しました。
私は「北風と太陽」の話が大好きです。北風ヒューヒュー吹いて、ああしろ、こうしろと言うよりも、ポカポカ太陽のようにやっていれば自然に人は上着を脱いでいきます。母のところに足を運ぶたびに7時間でも8時間でも母の溜め込んでいた愚痴を聞いていたら、母の口から「お前は偉いね」という言葉が自然と出てきました。余命3年と宣告されていたのが、もう5年以上になります。母のがん治療は、薬や抗がん剤とかではなくて、溜まっていたものを娘である私に吐き出させるのが何よりもがん治療じゃないかと思っています。本当に人間って溜まっている感情というものは、出して、感じて、消化させてあげるものだなと、母を通してつくづく思いました。人間は未解決な感情をたくさん抱えています。感情だって、日の目を浴びて認めてもらいたいのです。