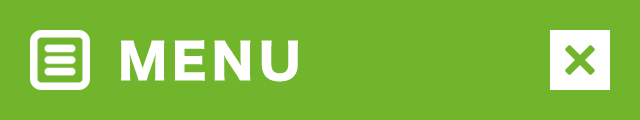精神疾患のある本人もその家族も生きやすい社会をつくるために
第2回:
幼稚園から小学校へ――孤独と葛藤のなかで見つけた小さな逃げ場

みなさん、こんにちは。2001年生まれの大学生で、精神疾患の親をもつ子ども・若者支援を行うNPO法人CoCoTELIの代表をしている平井登威(ひらい・とおい)です。
「精神疾患の親をもつ子ども」をテーマに連載を担当させていただいています。この連載では、n=1である僕自身の経験から、社会の課題としての精神疾患の親をもつ子ども・若者を取り巻く困難、当事者の声や支援の現状、そしてこれからの課題までお話ししていきます。
第1回では、父親が精神疾患を発症してから現在までを簡単にお話ししました。今回からは、もう少し詳しく当時を振り返ってみようと思います。第2回である今回は、そのなかでも幼稚園から小学校時代に焦点を当て、僕が経験した孤独や葛藤、そして支えとなった出来事についてお話ししたいと思います。
【著者】

平井登威(ひらい・とおい)
2001年静岡県浜松市生まれ。幼稚園の年長時に父親がうつ病になり、虐待や情緒的ケアを経験。その経験から、精神疾患の親をもつ子ども・若者のサポートを行う学生団体CoCoTELI(ココテリ)を、仲間とともに2020年に立ち上げた。2023年5月、より本格的な活動を進めるため、NPO法人化。現在は代表を務めている。2024年、Forbes JAPANが選ぶ「世界を変える30歳未満」30人に選ばれる。
父親の発病と家庭内の変化
父親がうつ病を発症したのは、僕が幼稚園の年長だった頃のことです。正直、発症前のことはあまり覚えておらず、発症前後の父の変化はわかりません。しかし、父のうつ病は、家庭全体に暗い影を落としました。
父は日によってまったく違う姿を見せるようになりました。
ある日は部屋に閉じこもり、誰とも話さないかと思えば、別の日には突然感情を爆発させ、怒りを僕や母、姉にぶつけることもありました。そんな父にどう接すればいいのかわからず、子どもながらに怯え、常に父の顔色をうかがうようになっていきました。
特に僕の小学校入学後、家庭内の状況はさらに悪化していきました。両親の喧嘩が頻繁に起こり、家具が壊れたり、ガラスが飛び散ったりすることもありました。時には包丁が持ち出され向けられたり、目の前で母親が首を絞められているような場面もあり、家庭のなかは常に緊張感に包まれていました。
「いい子」でいようとする努力
当時の僕は、小さいながらに「どうにかして家庭を保たなければ」と考え、「いい子」でいようと努めていました。親の機嫌を損ねないよう、常に空気を読み、自分の言動が家族の雰囲気を悪化させないように心を配っていました。
しかし、それはとても重いプレッシャーでした。本当はつらい気持ちや助けてほしいという思いがありましたが、誰にもそれを伝えることはできませんでした。当時はうつ病という言葉も知らず、他の家庭と自分の家庭を比べるなんて考えたこともなかったため、自分の過ごす環境が普通と思っていました。また、家庭のことを外で話してはいけないと思い込んでいたため、学校では家庭での悩みを隠し、友達や先生の前では明るく振る舞っていました。
学校での生活と孤独
学校では、表向きは「明るい普通の子」として過ごしていましたが、心のなかでは常に家庭のことを考えていました。例えば、授業中にふと「家でまた両親が喧嘩しているのではないか」と不安になることがありました。常にどこか家庭のことが頭から離れない自分がいました。
その結果、表面上は元気に見えても、内側では孤独を深く感じる日々が続きました。
後悔
自分の家庭が普通だと思っていたことから生まれた出来事で1つ強烈に頭に残っていることがあります。
小学校中学年のとき、2つ下の学年の男の子が泣きながら先生と話していました。僕はたまたまそこを通りかかり、その子が先生に
「お母さんが包丁を向けてくる」
と言っているのを聞きました。その子はずっと泣いていてそれを聞いて僕は疑問を感じたのです。
「えっ、それって普通じゃないの?」
当時小学生であり、世間を知らない自分にとってそれは普通であると思っていました。
先生がいなくなったあと、僕はその子に
「俺もそうだから大丈夫だよ」
と言ってしまいました。
今思うと最低です。
その言葉がその子にどんな影響を与えたかはわかりませんし、当時悪気があったわけでもありませんが、今でも後悔している出来事です。でも、そのような言葉が出てくるくらいには家族の状況は当たり前のことだったのです。
サッカーとの出会い
そんななか、僕にとっての小さな救いとなったのがサッカーでした。幼稚園の年長時にサッカーを始め、小学校に入学して地元のサッカーチームに入ることになり、本格的にサッカーをするようになりました。
サッカーはとにかく楽しく、夢中でボールを追いかける時間は、家庭の問題から一時的にでも解放される貴重な時間でした。友達と一緒にプレーすることで心が軽くなり、試合や練習で汗を流すことでストレスを発散することができました。
しかし、今後この連載でも触れていきますが、そんなサッカーがもつ意味も、時間の経過とともに徐々に変化していくようになりました。
改めて振り返って
幼稚園から小学校時代にかけて、僕は家庭のなかで孤独や葛藤を抱えながらも、「自分が頑張るしかない」と思い込んでいました。同時に、サッカーや友達との時間が僕の心の支えとなり、今思うとそれらが居場所だったのだと思います。
次回は、中学校時代の経験について振り返ります。家庭内での混乱が続くなかで、中学生の僕がどのように日々を過ごし、外の世界との関係を深めていったのかを振り返りたいと思います。

手前の青いユニフォームが僕です