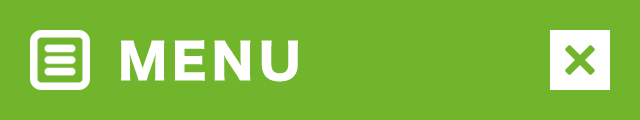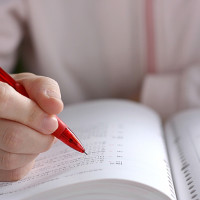再録・誌上ケース検討会
このコーナーは、月刊誌「ケアマネジャー」(中央法規出版)の創刊号(1999年7月発刊)から第132号(2011年3月号)まで連載された「誌上ケース検討会」の記事を再録するものです。
同記事は、3人のスーパーバイザー(奥川幸子氏、野中猛氏、高橋学氏)が全国各地で行った公開事例検討会の内容を掲載したもので、対人援助職としてのさまざまな学びを得られる連載として好評を博しました。
記事の掲載から年月は経っていますが、今日の視点で読んでも現場実践者の参考になるところは多いと考え、公開することと致しました。
第71回 50代のALSの利用者をどう支えるか
(2006年4月号(2006年3月刊行)掲載)
スーパーバイザー
高橋 学
(プロフィールは下記)
事例提出者
Sさん(居宅介護支援事業所・看護師)
提出理由
50代後半のクライアントは、妻とその母との3人暮らしである。発病後、機能低下が進行するのに比例して妻やヘルパーに対して介護に対する要求度が高くなってきた。介護者は皆最善を尽くしているが、クライアントは常に枯渇感を感じているかのように不満をぶつけてくる。クライアントを心の底から満足させることのできないケアマネジャーは、面接をするたびに無力感を感じてしまう。また、面接の際にクライアントに「こころの壁」を感じてしまうことに対するアドバイスをいただきたい。
かかわりのきっかけ
平成14年8月、前ケアマネジャーの異動に伴い交代する。それ以前に3事業者と契約していたが、クライアントの希望で本事業所に交替(平成13年8月。ケアマネジャーとしては5人目になる)。
前ケアマネジャーからは「クライアントは自分の主張するサービス以外は、勧められるだけでも不快感を示すので、こちらからは何も言わないように」と申し送りがあった。
利用者と家族の状況
- ・利用者:Jさん(男性・58歳)
- ・家族構成:妻(53歳)、妻の母、娘(28歳・別居)
- ・家族との関係等:本人は3人きょうだいの2番目。両親は他界している。本人が闘病生活に入ってからよく見舞いに来ていた弟も他界。姉は遠方に住んでおり、年に1~2回来訪する程度の交流。妻の母親は、妻が介護に専念できるよう家事一切を行っている。妻が苦労しているのを心配しているが、口を挟むことはない。2年前に結婚した娘は夫の仕事の関係で海外に在住しており、実家へは年に1~2回帰る程度。
- ここから先は、誌面のPDFファイルにてご覧ください。
プロフィール
高橋 学(たかはし まなぶ)
1959年生まれ。早稲田大学大学院博士後期課程満期退学。東邦大学医学部付属大森病院、北星学園大学を経て昭和女子大学大学院福祉社会研究専攻教授。専門は、医療福祉研究、精神保健福祉学、スーパービジョン研究、臨床倫理など。