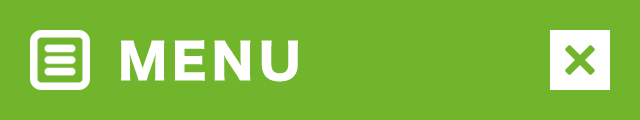福祉の現場で思いをカタチに
~私が起業した理由 ・トライした理由 ~
志をもってチャレンジを続ける方々を、毎月全4回にわたって紹介します!
【毎週木曜日更新】
Vol.78 連載第1回
「認知症だけには、なりたくない」と
言わなくていい、社会の実現を目指す

中島 珠子(なかじま たまこ)さん
コミュニティーナース
2014 年から認知症カフェ「たんぽぽカフェ」、2017 年からは若年性認知症本人と家族の集い「café マリエ」を主催。認知症になっても希望と尊厳をもって暮らし続けることができる社会を創りだす」ことを信念に、認知症のご本人や家族が集い、語らい、仲間づくりや情報交換の場を数多く企画・運営している。
取材・文 毛利マスミ
――中島さんの多岐にわたる活動について教えてください
認知症の方の「たんぽぽカフェ」と若年性認知症の方を中心とした集いの場「Café マリエ」という二つのカフェの運営と、暮らしのなかで困っていることならなんでも聞く「暮らしの保健室」。さらに、2025年1月からは区内外に関わらず情報交換できる場として「結の碧空(ゆいのあおぞら)」も開所しました。
超高齢者社会といわれるようになって久しいですが、「地域で最期まで暮らすことができない」と感じるようになり、地域でも「高齢者のこと、認知症についてもっと知ってもらわなきゃ」という危機感から、2014年から月1度開催で「たんぽぽカフェ」をスタートしました。
わたしが本格的に認知症カフェを運営するようになったのは、50代になって以降のことです。わたしは縁あって高齢者施設で看護師を務めておりましたが、認知症に対する理解は、社会的にはもちろんのこと、高齢者施設の職員でさえも全然足りていないと憤っていました。
わたしは40代からご近所さんを集めてお茶会を開いていたんです。高齢者もシニアも老若男女問わず地域の人たちと「つながる」ことを目的に、お互い・課題を「知る」活動をはじめていたのですが、仕事をはじめてからも休みの日にお茶会は続けていました。
「認知症になっても、いきなりなにもわからなくなってしまうのではない。認知症への偏見をなくして地域で暮らしていくためには、どうしたらいいのか」……他愛のないおしゃべりをしながら、認知症についても正しく知ってもらう。というようなことを目的にしていました。地域のことは、地域に暮らす人が一番よくわかっているのですから。
――たしかに認知症に対する偏見は、いまだになくなってはいないと感じます。お茶会では、どのようなことをなさっていたのでしょうか?
活動をはじめた当初は、お茶とお菓子を楽しみつつ、手芸的なことをしたり、折り紙を折ったりして、とにかく楽しんでもらいつつ、認知症についての話をしたり、ビデオを見たりしていました。でも、そうこうしているとみなさん、「認知症にだけはなりたくない」という話になってしまうことが多くて。認知症には誰だってなるんだよ、と、お伝えはするもののなかなか思ったように進めるのは難しく感じていました。
そんな折、当時東北福祉大学の矢吹知之先生を通じて、オランダでの認知症カフェの実践を知りました。「認知症カフェは、ただお茶を飲んで終わりではない」という理論は、いかにみなさんに認知症を正しく伝えるかを模索していたわたしにとっては目からウロコという感じでしたね。それで、本場オランダのノウハウによる、認知症カフェの企画・運営を学ぶ「認知症カフェモデレーター」研修を受講するために、すぐに仙台まで行きました。
その研修を受けて、本当に青天の霹靂というか……。これまでやってきたことは、ただの「サロン」だったことにあらためて気づかされました。
研修内容は一緒に運営をしてくれている仲間にも、伝えましたが、偏見のない「正しい認知症感」とでもいうのでしょうか、フラットな関係性について理解してもらうのには、1年ほどかかりました。「偏見」をなくすことは本当に難しくて、わたしだって偏見はゼロではありません。じっさい、認知症の当事者さんご自身もご家族も偏見を持っているんです。だから、とにかく「伝え続ける」ことしかないと思っています。
認知症と診断されたら、その人がきょうからちがう人になってしまうのではなく、「本人は変わっていない」ことを伝えたいです。最近は、高齢者の認知症に留まらず、若年性認知症についても報道されるようになり、少しずつ社会的な理解も進みつつあります。でも、仕事がまだできるのに辞めざるを得ない方もたくさんいらして、課題は多いと感じています。いまは、そうした当事者さんが書いた本もたくさんありますから、2時間のカフェ活動のなかで30分くらい朗読することもあります。
――ありがとうございました。
次回は、中島さんの人となりについておうかがいします。
第2回は2月13日(木)掲載
中島 珠子(なかじま たまこ)さん
1953年生まれ。看護師を勤めるが結婚を機に退職。その後、30年余のブランクを経て高
齢者デイサービスの看護師として復職した。一貫して、地域で暮らすこと、高齢者の課題、認知症の課題に目を向け、自宅を解放してのお茶会を在職中から開催。それが発展して、たんぽぽカフェ、café マリエなど、現在につながる活動となっている。体調を崩して 2019年に施設を退職した後も精力的に活動を広げ、コロナ禍の 2021年からは、仲間の看護師と一緒に「暮らしの保健室」を開所。多世代交流の場として活用しつつ、気楽な悩み相談の場を開いている。さらに、2025年1月からは、地域にこだわらない情報交換の場「結の碧空(ゆいのあおぞら)」もスタートさせた。

和気あいあいとした「たんぽぽカフェ」。毎月第2土曜に開催している。
●インタビュー大募集
「このコーナーに出てみたい(自薦)、出してみたい(他薦)」と思われる方がいらっしゃいましたら、terada@chuohoki.co.jp までご連絡ください。折り返し連絡させていただきます。
「ファンタスティック・プロデューサー」で、ノンフィクション作家の久田恵が立ち上げた企画・編集グループが、全国で取材を進めていきます
本サイト : 介護職に就いた私の理由(わけ)が一冊の本になりました。
花げし舎編著「人生100年時代の新しい介護哲学:介護を仕事にした100人の理由」現代書館