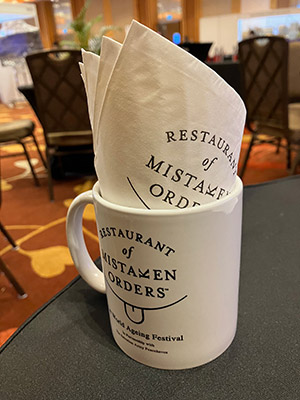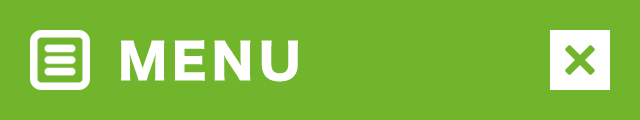和田行男の婆さんとともに

「大逆転の痴呆ケア」でお馴染みの和田行男(大起エンゼルヘルプ)がけあサポに登場!
全国の人々と接する中で感じたこと、和田さんならではの語り口でお伝えします。
- プロフィール和田 行男 (わだ ゆきお)
-
高知県生まれ。1987年、国鉄の電車修理工から福祉の世界へ大転身。
特別養護老人ホームなどを経験したのち99年、東京都で初めてとなる「グループホームこもれび」の施設長に。現在は株式会社大起エンゼルヘルプ地域密着・地域包括事業部 入居・通所事業部部長。介護福祉士。2003年に書き下ろした『大逆転の痴呆ケア』(中央法規)が大ブレイクした。
注文をまちがえる料理店inシンガポール

5月24日・25日の2日間、シンガポールで有名なホテル「マリーナベイサンズ」に隣接する「サンズエキスポコンベンションセンター」で開催されたエイジングアジア・ワールドフェスティバルにおいて「注文をまちがえる料理店at World Ageing Festival」を開催しました。

これは、フェスティバルを主催する現地法人からの要請に「一般社団法人注文をまちがえる料理店(以下「注文」)」がお応えしコラボレーション企画として実現したもので、僕らが関わった海外初の取り組みとなりました。

料理店を開催するにあたり、依頼されたことは「認知症の方への基本的な考え方のレクチャー」「注文をまちがえる料理店を開催する動機から実際までのレクチャー」「演習」「リハーサル」で、その意味は単発の取り組みで終わらせてはならないと考えてのことのようです。
20日(土)初日、現地ナーシングホーム(以下「ホーム」)において、注文をまちがえる料理店に携わってくれるサポーターの方々(ホーム職員)に、僕がどんな考えや想いで認知症の状態にある方への生活支援に取り組んできたかについて話しました。
22日(月)二日目、今度は「注文」の取り組みについて、そのきっかけやコンセプト、日本や世界における広がりなどを「注文」の理事からプレゼンテーションさせていただきました。
そのうえで、料理店でホールスタッフとして働かれる認知症の状態にある方々(ホーム入居者・利用者)をサポートする職員さんたちと一緒にホームのカフェ・スペースを使って演習を行いました。

23日(火)三日目、同メンバーで会場においてリハーサルを行いました。料理店の飾りつけを行いながらですから、おのずと緊張感が高まってきます。
そして、24日(水)25日(木)10時・13時・14時の計6回、ホールで接客係を担ってくださる認知症の状態にある方々を迎えて最終的な打ち合わせを行い、本番を迎えました。

こんなに丁寧にコラボレーション企画で開催するのは初めてでしたが、ナーシングホームでの演習に入るとサポーターとなるホーム職員さんがとても積極的で、あれこれ提案してくださったり、場を和まし合いながら進めてくださったり、とても良い雰囲気で本番を迎えることができました。

僕が強調したことは、「ご本人たちが困ったときにそっと手を差し伸べること」「焦らなくてよいこと」「お客さんと一緒に愉しもう」ということですが、日本での開催を見てもそうですが、これがなかなか難しいんです。
本番初日、何も言わずそっと見ていましたが、職員さんたちは待てないですね。ぴったりと付き添い関わりすぎてしまいますので、本人たちの持てるチカラを発揮する機会がない。僕にはそう映りました。

そこで二日目はオペレーションを変えて、職員さんたちをホールスタッフから離し、四テーブルある四隅に配置することにして、ホールスタッフが困っていたら関わってくださいと指示を出させていただきました。
するとどうでしょう。
文字にするのは難しいのですが、ホールスタッフに「自ら行動される姿」「お客さんと会話をする姿」が一気に増えました。もともと能力の高い方々だったということで、職員さんが傍にいない分、チカラを発揮することにバリアがなくなったからです。

シンガポールでは、ピッチャーに水を入れてテーブルを回って「お水はいかがですか」と聞くこと・注ぐということがないそうで(実際、何件かのレストランに行きましたが、一軒を除いてミネラルウォーターをボトルで注文でしたもんね)、その習慣がない土地でそれをホールスタッフにやっていただくオペレーションを初日から強引に押し付けましたが、それも二日目は自発的にされる方が現れましたもんね。

また、お客さんの方も、食べているときにホールスタッフにテーブルに来られる・話しかけられるのも嫌がる方が多いようで、それは見ていても感じましたが、それも突破していましたね。
というのも二日目は、僕ら「注文をまちがえる料理店プロジェクト」の一般参加者向けプレゼンテーションがあったので、お客さんの多くは「注文をまちがえる料理店」の話を聞いて、わかった上で来られている方が多かったからではないかと思いました。

シンガポールの方や香港、オーストラリアの方々からも「やりたい」と声があがってきましたし、常設店の声も聞こえてきていますが、どうあれ大事なことは、認知症の状態になっても人生を諦めさせない社会のあり様を追求することであり、そのためには社会全体が認識を共有し合うことで、それは日本だけのことではなく、これから急速に高齢化を迎える国々にとっては、認知症の原因疾患根治薬などが登場しない限り、長寿と共についてくる社会的課題ですからね。
地域社会とかけ離れた場所へ隔離する施策をとるなら話は変わりますが、地域社会の一員として暮らせる社会を目指すなら、認知症からくるズレを認知症の状態にない者が埋めていくことが必要なのですから。