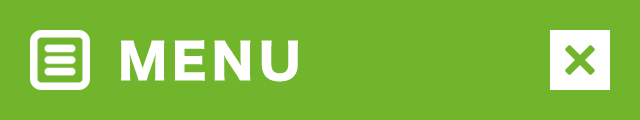知ってるつもりの認知症ケア
第1回 教科書だけじゃわからない?

認知症の人に接するときには「認知症の人の見ている世界」を正しく理解することが大切です。それによって適切で質の高いケアを提供でき、利用者は認知症になっても安心して生活することができます。
……とはいっても、さまざまな仕事をこなす日々の業務のなかでは、理想どおりのケアを行うことは一苦労です。
この連載では、認知症ケアの第一人者である理学療法士の川畑智さんのもとに、悩み多き介護職の方々が訪れ、ともに「現場のリアルな困りごとを理想に近づけるためのヒント」を模索していきます。
理想論ではなく、認知症ケアのリアルなつまずきにスポットを当ててみたいと思います。
Aさん:川畑さん、はじめまして。介護の仕事を始めて3年目のAです。今回、僕の悩みを聞いてくれると、施設長に紹介されてきたんですけど……。
川畑:はじめまして! 理学療法士の川畑智と申します。もちろん、なんでも聞いてくださいね。答えを一緒に探していきましょう。
Aさん:ありがとうございます。さっそくなんですけど、認知症のある人への対応って、正直困ることが多くって。よく「言動の背景をしっかり見極めて、本人の不安に寄り添うことが大事だ」とかって言われますけど、できることはすべてやってるし、どうしたらいいのかわかりません。
川畑:認知症のある利用者さんへの困りごと。介護していれば、誰もが経験する「あるある」ですね。実際の介護現場では、勤務時間のなかで多くの利用者のケアにあたるわけですから、ギリギリの状態になっていることもあるかもしれないですね。突然ですが、Aさんはこれまで利用者に虐待したことがありますか?
Aさん:虐待!? ないですよ!
川畑:まあ、こんなふうにストレートに聞くと「あります」なんて素直に答える人はあんまりいないとは思います。では、「これって不適切なケアかも」と思いながら介護をしてしまったことはないでしょうか?
Aさん:そう聞かれると、まったくないと言い切る自信はないです。たしかに「ちょっと強く言っちゃったかな」みたいなことは……。
川畑:おそらく介護の仕事をしていれば、けっこうな人が「ある」と答えるんじゃないかなと思います。昔のことも「思い返すと不適切だったかも」と考えることがあるかもしれませんね。
Aさん:そうだと思います。
川畑:実は、ここには言葉のマジックがあるんです。2つの質問を続けてしたことで「虐待」と「不適切なケア」が別物のように感じたかもしれませんが、実はこの2つはまったく異なるものじゃないんですよ。
Aさん: 別物じゃないって、どういうことですか?
川畑:つまり、適切なケアと不適切なケア、または好ましいケアと好ましくないケアと言ってもいいんですけど、これらは同じ軸にあって切り離せるものではないんです。例えるなら、一本の鉛筆みたいに端と端は延長線上にある感じですね。不適切なケアを続けていると、気づかないうちに虐待になっている、なんてこともあるわけです。逆に、虐待になる手前で、不適切なケアが好ましいケアに変わるチャンスもあるとも言えます。
Aさん:なるほど。そんなふうに考えたことなかったです。
川畑:実は告白すると、私もかつて不適切なケアをしたことがあります。理学療法士として働き始めた1年目のとき、リハビリにのってくれない認知症の患者さんがいて、声をかけると私の腕をつねったり、引っ掻いたり、噛みついたり。それが嫌で嫌で……たまりかねて「何をするんですか!」と払いのけたり、「こうしたら痛いじゃないですか!」と軽くつねるふりをしてみたり。この気持ちをどうにかわからせたいという思いでした。だけど、今となっては間違いだったと思いますよ。やっぱり一番の問題は、認知症の人がなぜこのような言動をするのかを理解できていなかったことです。
Aさん:うーん。認知症については僕もひと通り勉強しましたけど、現場にいたらそれどころじゃないですよ。僕がいる施設には、トイレに何度も行きたがる利用者がいて、ひどいときには10分おきに呼ばれるんですけど、さすがに「またか!」と思っちゃいます。
川畑:わかります。ただ、答えを急がず、ゆっくりいきましょう。私たちケアを提供する側は、何度も何度もトイレに行きたいと言われると、「さっき行ったばかりでしょ!」と思ってしまいますよね。
Aさん:実際そうですよね。もう連れて行ったのに……って。
川畑:ですよね。ただ、それは私たちが「この人はさっきトイレに行ったばかり」という事実を覚えているからなんですよ。認知症ではない私たちが見ている世界では「先ほどの続きの自分」がいて、すごろくのように進んだ場所を覚えているわけです。それに対して認知症の人は、どこまで進んできたのかがわからなくなっちゃう。これが短期(即時)記憶障害と呼ばれていて、そのせいで記憶が抜けてしまうということはどこかで聞いたことがあると思います。
Aさん:はい、どの教科書にも真っ先に書いてあります。
川畑:そうですよね。ただ、言葉としてはわかっていても、実際に何度もトイレに行きたいと言われると「なんでわかってくれないの?」と思うかもしれません。何が原因だと思いますか?
Aさん:この流れでいくと、認知症の人の世界で見ようとしていないから……ですか?
川畑:まさにそうです! 認知症の人の言動を自分の物差しで物を測ってしまっている、と言ってもよいかもしれません。「私はわかるのに、なんでこの人はわかってくれないんだろう」と。このとき、利用者の世界ではなく、「先ほどの続きの自分」を物差しにして、相手(=認知症の人)の言動を判断しているわけです。
Aさん:そういわれると、そうですね。
川畑:私たちは認知症について「知識」として理解していても、本当の意味では理解できていないかもしれません。これは経験に関係なく、私たち自身が認知症に対して「認知症」になっていないか? と疑うことが大事なんだと思います。
Aさん:僕たちが認知症……?
川畑:私たちは知識があっても、いざというときには忘れてしまうんですね。認知症の人の見ている世界を見る姿勢を忘れないようにしましょう。そのための道のりは長いですよ! 次回は、先ほど例に出したトレイに何度も行きたがる利用者について、考えていきましょうか。
Aさん:なんだか大変そうだけど、なんとかついていきますよ。
※次回は、何度もトイレに行きたがる利用者のことを取り上げて、認知症の人がどんな世界を見ているのかを深掘りしていきます。
川畑智さんのプロフィール
理学療法士、熊本県認知症予防プログラム開発者、株式会社Re学代表
1979年宮崎県生。病院や施設で急性期・回復期・維持期のリハビリに従事し、水俣病被害地域における介護予防事業(環境省事業)や、熊本県認知症予防モデル事業プログラムの開発を行う。2015年に株式会社Re学を設立。熊本県を拠点に病院・施設・地域における認知症予防や認知症ケア・地域づくりの実践に取り組み、県内9つの市町村で「脳いきいき事業」を展開。ほかに脳活性化ツールとして、一般社団法人日本パズル協会の特別顧問に就任し、川畑式頭リハビリパズルとして木製パズルやペンシルパズルも販売。年間200回を超える講演活動のほか、メディアにも多数出演。著作に『マンガでわかる! 認知症の人が見ている世界』シリーズなど。