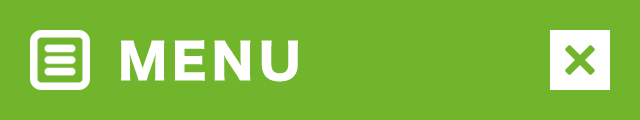上手に怒れる親になろう!
子どもを怒らずに育てたい! そんなパパ・ママに吉報
アンガーマネジメントでストレスフリーな育児をしよう

「何回言ったらわかるの!」「いい加減にしなさい!」
子育てをしていると、つい子どもに投げかける言葉ですね。言った後で「少し言い過ぎたかな」「もっとやさしく言えばよかったかな」と後悔したパパ・ママもいることでしょう。
そんな後悔をしないためにも、アンガーマネジメント流言葉かけを学んでみませんか?
1 子育て家庭のお悩みは?
「令和2年度『家庭教育の総合的推進に関する調査研究~家庭教育支援の充実に向けた保護者の意識に関する実態把握調査~』報告書」(株式会社インテージリサーチ、令和3年2月)では、子育て家庭の悩みや不安について、およそ3400名のパパ・ママのアンケートをまとめています。
パパ・ママの半数が「叱り方」に関心あり!
パパの悩み第1位は「しつけの仕方がわからない」(44.6%)。対してママの悩み第1位は「子供の生活習慣の乱れについて悩みや不安がある」(44.7&)となっています。前述のきつい叱り方につながると思われる「子供との接し方が分からない」は、パパ15.2%、ママ12.3%、「子供の気持ちが分からない」は、パパ29.2%、ママ29.7%と高い回答率となっています。
「家庭教育について知りたい情報」では、「子供のほめ方・叱り方」がパパ52.0%、ママ43.5%と非常に高い関心があり、子どもの気持ちや接し方がわからない→どのようにほめてよいのか・叱ってよいのかわからないという悩みがみてとれます。
2 専門家に聞いてみた!
このように、世の多くのパパ・ママが悩む叱り方について、もう少し深堀りしたいと思い、感情保育学研修所代表で日本アンガーマネジメント協会アンガーマネジメントコンサルタントの野村恵里さんにお話を伺いました。
――子育ての際、つい子どもに声を荒げてしまうのはなぜでしょうか?
野村 子育て中は、何かと子ども中心の生活に偏りがちです。特に乳幼児期の子どもの場合には手がかかることも多いため、大変、忙しい、疲れるなどネガティブな感情を抱えてしまうこともあります。そんなとき、子どもが言うことを聞いてくれなくて自分の予定通りに物事が進まないと、イライラが募ってしまうのも仕方がないことかもしれません。「こんなにがんばっているのに」「なんでわかってくれないの」そんな不満や不安が怒りの感情となって、自分より弱い立場の子どもにあたってしまうことがあります。感情的になってしまうと衝動のコントロールができにくくなるため、声を荒げてしまう行動をとってしまうことがあるのかもしれません。でもそれは、一生懸命子育てをがんばっている証拠ともいえるのです。ほんの少し表現の仕方を変えてみると、声を荒げなくてもいいことが増えてくるかもしれませんね。
――なるほど。それでは、子どもに対してきつい言葉かけをすると、どんな悪影響が出るのでしょうか?
野村 子どもは身近な大人の表現方法を模倣します。日常的にきつい言葉かけをされる環境で生活していると、子どもも同じような話し方をするようになります。日々の経験から、それが普通のことだと思うからです。ところが、それを聞いた大人は生意気だ、口答えをしていると感じてしまうかもしれません。周りの友だちからは、怖い、嫌だと思われてしまうかもしれません。人とコミュニケーションをとるときの話し方はとても重要です。同じ話をしても、言い方の違いで相手に与える印象は変わります。言葉の選び方や話し方にほんの少し気をつけるだけで、親も子も人間関係のトラブルを減らすことができるかもしれません。
――親の背中を見て子どもは育つわけですね。野村さんが専門としているアンガーマネジメントは、子育てに応用できるのでしょうか。
野村 子育てにおけるアンガーマネジメントとは、子どもをむやみやたらに怒らないことかな、と思っています。「つい怒ってしまった」「ストレス発散で」「むしゃくしゃしていたから」など、子どもに説明できない理由で怒らないようにすることです。一方で、なぜ怒っているのか、そして、これからどうしたらいいのかの解決方法などを、子どもが理解できるように伝えてあげられるなら怒ってもいいのがアンガーマネジメントです。「怒らない親になりましょう」と言っているわけではなく、「上手に怒れる親になりましょう!」というのが、子育てにおけるアンガーマネジメントの考え方です。
――「上手に怒れる親」にならなれそうです(笑)。アンガーマネジメントのテクニックを使えば、子どもにやさしくなれますか。
野村 優しくなれます! 言葉かけも変わります! が、すぐにはできるようになるわけではありません。アンガーマネジメントは心理トレーニングなので、日々少しずつ練習していくものです。できる日もあればできない日もあります。それでいいんです。大事なのは続けていくこと。アンガーマネジメントのテクニックを使って、「ちょっと優しくなれたかも」「いい感じの言葉かけができたかも」という自分のがんばりや変化を褒めてあげてほしいです。気づいて、褒めて、嬉しくなって、笑顔が増えたら、子どもも変わってきます。一歩進んで二歩下がる程度のスピードで大丈夫。怒り過ぎたら「ごめんね」と、素直に謝れる自分にも花丸を上げてくださいね。
――自分に花丸を上げるためにも、アンガーマネジメントを学びたいですね。

野村恵里(のむらえり)
感情保育学研修所代表、旭川荘厚生専門学院児童福祉学科特任講師。日本アンガーマネジメント協会アンガーマネジメントコンサルタント。
岡山生まれ、岡山育ちの元保育者。2012年、子育てと仕事の両立でイライラがつのる生活から脱出するため、アンガーマネジメントを学ぶ。現在は、アンガーマネジメントに救われた自身の体験をもとに、保育、子育て現場で日々子どもに向き合いがんばっている方にアンガーマネジメントをお届けする講師活動をしている。著書に『保育者のためのアンガーマネジメント入門 感情をコントロールする基本スキル23」(2017年、中央法規出版)、『保育者のための子どもの「怒り」へのかかわり方 アンガーマネジメントのテクニック』(2018年、中央法規出版)、『子どもの感情表現を育てるあそび60』(2020年、中央法規出版)、『もうイライラしない!保育者のためのアンガーマネジメント』(2022年、チャイルド本社)、『とっさの怒りに負けない子育て』(2023年、すばる舎)などがある。
関連書籍のご案内
 今回お話を聞いた野村恵里さんの新刊、『イライラを爆発させない! パパ・ママが楽になる子どもの叱り方 子育てにいかすアンガーマネジメント』の詳細はこちらから。 |