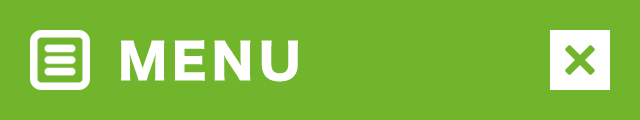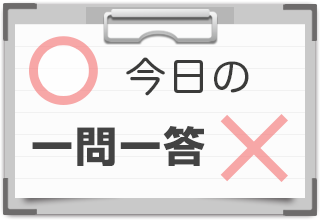第37回社会福祉士国家試験 問題の講評
第37回社会福祉士国家試験 <共通科目>問題の講評
ご無沙汰しております。東京学芸大学の露木信介です。特別編として2回に分けて国家試験の講評をします。
まずは皆さん、大変お疲れさまでした。試験からまだそれほど時間が経っていませんが、解答速報や問題の見直しなどをして、少し冷静に試験を振り返れるようになったのではないでしょうか?
ただ、合格ラインはまだわかりませんので、合否に関係なく、第37回試験の振り返りをしておきましょうね。合格した人は、さらに現場実践での「知」となりますし、不合格だった人は、来年度の受験に向けて、反省したり課題を見つけ出したりと、準備を進めることができます。合格発表までの時間を有効に使ってください。
それでは、今回は、<共通科目>問題の講評です。
Lessen.1 〈共通科目〉問題の総括
2回に分けて、第37回社会福祉士国家試験の講評を行いたいと思います。今回は、<共通科目>問題(精神保健福祉士との共通科目の問題)についてです(解答速報はこちら)
<共通科目>の試験科目は以下の12科目で、試験時間は10時から12時20分までの140分(2時間20分)でした。
■ 医学概論(6問)
■ 心理学と心理的支援(6問)
■ 社会学と社会システム(6問)
■ 社会福祉の原理と政策(9問)
■ 社会保障(9問)
■ 権利擁護を支える法制度(6問)
■ 地域福祉と包括的支援体制(9問)
■ 障害者福祉(6問)
■ 刑事司法と福祉(6問)
■ ソーシャルワークの基盤と専門職(6問)
■ ソーシャルワークの理論と方法(9問)
■ 社会福祉調査の基礎(6問)
講評ですから、短絡的に「難しい問題でした」とか、「やさしい問題でした」とか、「よい問題でした」とか、「悪問でした」とか主観的なことはあまり書かないようにしたいと思いますが、そうは言っても…。まず、私が実際に解いてみた感想を少し述べると、問題自体は、基本的な内容を問う問題を中心に、「現代の社会問題や福祉に関する知識」が問われ、全体的な印象としては、「過去問題や基礎知識をベースに、関連する新たな知識や、それを活かす応用力が必要でした」というところでしょうか。
このことから、過去の問題とその設問文から芋づる式に関連知識をきちんと学習していれば解答できる内容が中心でしたので、「昨年度(第36回)試験の難易度に比べ、同程度の難易度〜やや軟化(易しい内容)」という印象です。ですから、昨年度第36回試験は、6割90点以上の得点があった者を合格としていましたので、129点満点の今回(第37回)試験の合格ラインは、77点〜82点のあたりに合格ラインが設定されるのではないでしょうか。詳細をもう少し記してみると、午前の共通科目、午後の専門科目共に、昨年よりも更にやや易しくなった印象がありますが、まずは基本をきちんと押さえておくことで大きな失点にはならなかったと思います。
皆さんは、どんな感想や印象ですか?
過去の国家試験問題や、各種模擬問題をはじめ、「制度や統計、基本的事項をしっかりと押さえていた方は、かなり明確、明瞭に解けた問題が多かったのではないでしょうか。
一方で、各科目で新たに問われた項目もありました。ただし、多少、用語や法律・通知、人名などがわからなくても、設問文をしっかり読み、その内容や時代背景、福祉の変遷や動向などをしっかり捉えることで、正答までたどり着ける問題が多くありました。そういった意味では、一つひとつの設問の誤りを指摘できる力が必要でしたので、項目に対する関連知識が必要となります。
このように、社会福祉士・精神保健福祉士の試験では、福祉の動向や変遷などをきちんと理解しておくことが重要であることがわかります。
Lessen.2 科目別分析と講評
医療概論については、例年通り出題基準から幅広く出題されています。各問題をみてみると、定番ですが、問題1の「各発達段階(今回は、思春期・青年期)における心身の特徴」に関する問題が問われています。このほか、問題4では「難病」について、法律や制度に基づく問題が出題され、問題5では「肺炎」に関する臨床の問題が出題されました。さらに、問題6では「精神疾患患者に対する入院形態に関する事例問題」が出題されました。以上、基本的な内容でしたが、出題基準から幅広く出題されました。
心理学と心理的支援は、広範囲な事項が満遍なく出題されていました。問題7、8では、「心理学概論の基礎的な知識」が問われました。このほか、定番ですが、問題9で「エリクソンの発達段階の心理社会的危機(青年期)」に関する問題が出題され、ストレスに関する問題としては、問題10で「レジリエンス」に関する用語について問われています。最後に、問題12では、心理療法(認知行動療法)に関する基本的な内容が出題されました。残念なのでは、心理検査についての出題がなかったことでした。
社会学と社会システムから続く社会学系の科目が苦手の人は多いですが、社会学系の科目は、現代社会を学問的に捉える力を試すものです。つまり、現代社会の問題と、それを科学的に整理する力(理論:人名や功績など)が必要になります。
今回も、人名をはじめ、理論、用語などが出題されています。実際の問題を見てみると、問題13は「社会集団」に関する用語について問われ、問題14では「都市」に関する人名や功績について問われています。このほか時事的な内容としては、問題15で「過疎関連法」「過疎対策の現況」に関する問題や、問題16では「国民生活基礎調査の現況」を根拠とする統計に関する問題が出題されました。
社会福祉の原理と政策は、まず、現代社会の問題をきちんと理解していることが重要となります。そして、それを社会福祉学的に理解するために必要な項目が出題されていました。内容的には、やや難しく感じたり、苦戦した方もいらしたかもしれません。
具体的な内容を見ておくと、問題19では「英国におけるM。サッチャーの「小さな政府」への転換」をはじめ、問題21では「B。ニィリエのノーマライゼーション」について問われています。このほか、国内に関する内容としては、問題20で「大正期の社会事業(方面委員制度)」や問題25の「福祉の措置」、問題26の「社会福祉法に定められた福祉に関する事務所(福祉事務所)」について問われています。さらに、現代的な社会を外観する内容としては、問題22で「持続可能な開発目標の「極度の貧困(世界貧困線)」の参照基準や、問題23の「多文化共生の実現に向けた取組に関する施策など」、問題25の「国民の健康の推進の総合的な推進を図るための基本方針」、問題27の「間接差別の事例」について問われています。残念ながら、重要となる教育政策や時事的な内容の出題がありませんでしたが、現代のソーシャルワーカーは、「いかに現代社会の動向に関心を向けているか」が重要で、日頃から新聞やニュースなどを通して時事に精通しておく習慣が大切ですね。
社会保障については、基本的な項目が出題されています、わが国の社会保障の仕組みを理解するために基礎的な知識です。社会保障とは、「働く人が支える仕組み」ですので、現代の「働く人」の状況を的確に理解する力が必要です。現代の「働く人」の実情については重要ポイントです。労働人口や人口の動向や推計については、必ず整理しておかなければなりません(今回の出題はありません)。同様に、「社会保障費用統計」などの統計資料に目を通し、社会保障の費用等について理解しておくことが重要です(問題30)。
また、社会保障とは一言で「私(個人)の“困った”を社会全体で支える仕組み」といえます。その「私(個人)の“困った”」とは、「働けなくなって生活費“困った”(年金保険)」であり、「医療や介護で“困った”(医療保険/介護保険)」であり、「失業や働き、仕事中の病気や怪我で“困った(労働保険)」ということです(社会保険)。このほかに、「生活に困窮して“困った”(生活保護)」「子育ての費用で“困った(手当等)」などもありますね(公的・社会扶助)。このような「私(個人)の“困った”」を「社会全体」で支えることを社会保障と言います。試験問題では、日本の社会保険を外観するような問題が出題され、この他、年金保険、医療保険、介護保険、労働保険について出題されました(事例問題を含む)。具体的には、問題28では「社会保障制度の加入に関する事例問題」、問題31は「社会保障の給付に係る国の負担」、問題32と問題34は「社会保険の適用等に関する事例問題」、問題35は「雇用保険制度」について問われています。このほか、問題36で「諸外国における公的医療と公的年金」について出題されています。以上、社会福祉士にとって、社会保障に関する知識は重要となりますので、わからなかった問題は必ず復習しておきましょう。
権利擁護を支える法制度は、(1)憲法・民法・行政法、(2)成年後見制度、(3)権利擁護といった構成で出題されました。印象としては、旧カリの同様の科目に比べ(3)権利擁護に関する内容が充実していました。
具体的な内容を見ていくと、(1)憲法・民法・行政法では、憲法や行政法に関する出題はなく、問題37で民法における「三親等の親族(甥の配偶者)」を問う内容が出題されています。出題数が6問と限定されているので、仕方ないかもしれませんが、社会福祉士の必要な知識として、相続・遺言や行政訴訟や不服申立てなどについて出題されました。(2)成年後見制度に関する内容としては、問題41で「成年後見制度の利用促進」や、問題42は「成年後見の開始が被成年後見人に及ぼす影響に関する事例問題」が出題されています。こちらも、社会福祉士の必要な知識として、後見人等の役割や具体的な業務内容、代理権や同意・取消権などに関する内容が求められれます。
最後に、(3)権利擁護については、問題38では「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待への対応に関する事例問題」をはじめ、問題39「障害者差別解消法」、問題40「権利擁護の方針に関する事例問題」が出題されています。こちらについては、社会福祉士にとって、非常に重要な内容を含み、権利擁護=虐待や暴力・搾取については、ソーシャルワーカー定義(グローバル定義)や社会福祉士の倫理綱領等でも、「人権」の理念を重視していますので、それを根拠とする各種の虐待防止法については、必ず整理しておきましょう。この他、出題が予測されていた日常生活自立支援事業については出題がありませんでした。
地域福祉と包括的支援は、幅広い分野から問題が出題されていました。また、今回(第37回)試験より、(1)地域福祉や包括的支援体制の他に、(2)福祉行財政や福祉計画が出題範囲となっています。
具体的な内容をみていくと、(1)地域福祉や包括的支援体制については、問題48ではズバリ「包括的支援体制」に関する具体的内容を問う問題や、問題51では「重層的支援体制整備事業を所管する社会福祉士の対応事例」について問われています。このほか、問題49では「社会福祉協議会の地区担当(社会福祉士)の今後の対応に関する事例問題」や、問題50は「災害時の支援」に対する問題も出題されました。次に、(2)福祉行財政や福祉計画については、問題44で「「地方財政白書」の民生費」について問われ、問題45で「「地域福祉(支援)計画策定状況等の調査結果概要」の調査結果」について出題されています。出題されなかった内容としては、国と地方の関係や、社会福祉法を根拠とする地域福祉推進に関する内容などです。
障害者福祉は、昨年同様に、基礎的な内容を問うものが多く出題されていました。具体的に見ていくと、定番化された内容としては、問題52「生活のしづらさに関する調査」「障害者雇用実態調査」「障害者白書」を根拠とする「障がい者の生活等の実態」に関する問題が出題されています。このほか、「障害者総合支援法における基幹相談支援センター」に関する問題(問題53)をはじめ、「障害者雇用促進法(問題56)」や「障がい者への雇用支援に関する事例問題(問題57)」が出題されています。やや残念だったのは、「障害者総合支援制度にける具体的な福祉サービス(給付内容や専門職等)」に関する内容が問われていないことや、「障害者福祉制度の発展過程」など出題されていないことです。また、「障害者差別解消法」や「精神疾患患者の入院形態」については、他の科目と重複していたことについては改善の余地があると思います。
刑事司法と福祉で出題された項目は、(1)刑事司法と、(2)更生保護制度の二つに大別されますが、広範な内容が問われています。
まず、(1)刑事司法からは、問題58の「犯罪の成立要件と責任能力」をはじめ、問題59の「事例をもととする刑事手続」が出題されました。また、(2)の更生保護制度については、刑務所等の「施設内処遇」に対して「社会内処遇」を意味し、具体的には、①仮釈放、②保護観察、③更生緊急保護、④恩赦、⑤犯罪予防活動について出題されます。問題60では「刑の全部執行猶予中の保護観察に関する事例問題」が出題されています。ここでは、指導監督(一般遵守事項/特別遵守事項)と補導援護に関する基礎的な知識が問われています。合わせて、「更生保護に係る人や組織」(問題61)について問われていますが、ここでは、保護観察官や保護司、地方更生保護委員会、保護観察所などについて整理しておきましょう。また、問題61では、定番化されていますが「「医療観察法」における地域処遇に関する事例問題」が出題されています。このほか、問題63では「犯罪被害者等基本法」について問われています。
ソーシャルワークの基盤と専門職は、「ソーシャルワークの理論と方法」、そして午後のソーシャルワークの基盤と専門職(専門)「ソーシャルワークの理論と方法(専門)とセットの科目といえます。本科目は、社会福祉士やソーシャルワーカーの倫理、価値に重きが置かれ、社会福祉士にとって重要な原理・原則についても取り扱われます。これに、ソーシャルワークの歴史的変遷や相談事業や援助といった内容も含まれます。
具体的には、問題64「社会福祉士(法)」、問題65「ソーシャルワーク専門職の定義(グローバル定義)」などからはじまり、問題68の「ソーシャルワークの形成(発展させた人物)」では、「アメリカにおける初期のセツルメント」について出題されました。このほか、「ノーマライゼーションの原理をもととした社会福祉士の発言に関する事例問題(問題66)」や問題69では「R。ドルゴフによって示された倫理原則」について問われています。残念だったのは、令和2年に改定された社会福祉士倫理綱領が全く触れられていなということです。残念です。これから実践する皆さんは、新たな社会福祉士倫理綱領について、必ず一読しておいてください。
ソーシャルワークの理論と方法の問題数は全9問(午後の「専門」を含めるとと「18問」)と、全科目のなかで一番配分が大きい科目です。本科目でしっかりと得点できていることが合格の必須条件だと思います。本科目では、「理論・アプローチ、モデルに関する問題(問題71、72)」や「ソーシャルワークの過程に関する問題(問題74、75)」、「社会福祉士の対応事例(問題73)」が例年同様に多く出題されました。出題形式は、応用問題というよりは一問一答的な問題の作りでした。この他、毎年出題されている「スーパービジョン(問題78)」の事例問題については基本的な内容を問うものでした。また、グループワークについては、問題76で「G。コノプカの原則」を基礎的な問題と、問題77では「グループワークの波長合わせを問う事例問題」が出題されました。
社会調査の基礎は、昨年度に同様の難易度で、更に基礎的な知識や内容を問う問題が多く、全滅(0点)という方は少なかったのではないでしょうか。
具体的な内容をみて行きたいとおもますが、まず、社会調査の基礎としては、問題79で「C。ブースのロンドン調査」や問題80で「調査における倫理」について問われています。このほか、具体的な調査の知識や技術については、問題81の「多肢選択法による質問紙調査」と、問題82の「調査票の配布・回収」については事例で出題されています。また、問題83では「散布図=2つの量的変数(ここでは、水分接収量と夜間の睡眠時間)の関係を見る時の方法」について問われました。さらに、問題84は「面接調査」における具体的な内容について問われています。このほか、調査手法の代表的なものに、質問紙法や観察法がありますので合わせてチェックしておきましょう。
「ありがとう」って大切なことばですね。。
以上、雑駁ですが、第37回社会福祉士国家試験の午前<共通科目>問題の講評でした。
すでに、受験した方から試験の感想を耳にしていますが・・・。皆さん、やはり不安なようです。本年度の試験は、基礎をしっかりと積み上げ、それを活用できる力を養ってきた人(やはり、過去問解説集や模擬問題集などをしっかりと、繰り返し解いてきた人)は、相当の得点ができたと思います。そういった意味では、わかっていた問題をミスで間違えたり、できる問題を落としたりといった小さなミスが合否に大きく影響する可能性があります。
一発勝負の試験ですので、当日の体調や心の動き、さまざまな環境要因や状況などは、合否に影響を与えます。皆さんいかがでしたか。ただ、何はともあれ、結果は結果。それを真摯に受け止め、これからの実践に活かしていってほしいと思います。
冒頭でもお話ししましたが、合否に関係なく、もう二度と見たくない、開きたくない試験問題、テキストかもしれませんが(笑)、ここで復習しておくことが、必ずこれからの力になります。
あともう一回、「特別編(2) 第37回社会福祉士国家試験・午後<専門科目>問題の講評」をお送りします。
この数ヶ月間、国家試験勉強を優先にして、保留していたこと、抑えていた気持ち、我慢していたこと・・・を解放してくださいね。今まで止まっていた時間を前に進めてください。社会福祉士は、人の生活と人生を支える仕事ですから、そういった意味では、人間的活動(人間らしい生活)が何よりも大切です。
あと、自分の周りにいる人を大切にすることが重要ですね。この試験が終わって、合否のことばかりで・・・支えてくれた大切な方に、「ありがとう」って、まだ感謝の言葉を伝えられていない方は、今すぐに行動しましょうね。「ありがとう」って。
社会福祉士は、ヒューマンサービスですから、相手がいなければ、支援もないし、サポートしてくれる仲間がいなければ支援なんてあり得ませんからね。感謝の心が大切ですね。私も常に心がけ、意識していることです。
- ■お知らせ■
-
本講座とは直接関係性はありませんが、私のメールマガジン【社会福祉士をめざす「露木先生の合格受験対策講座」】があります。こちらの講座では、勉強方法やマル秘話、独学や勉強時間がない方を対象に開講しています。また、4月からは第38回社会福祉士国家試験に向けた講座がスタートしました。気になる方は、チェックしてみてください。
- ※上記メルマガ【社会福祉士をめざす「露木先生の合格受験対策講座」】は、中央法規出版及び本講座「けあサポ」との関係はありません。そのため、本メルマガの問い合わせに関しては、中央法規出版では対応しておりません。