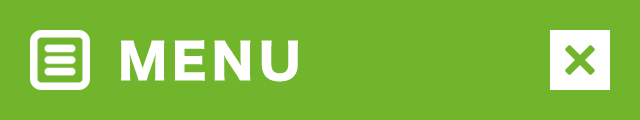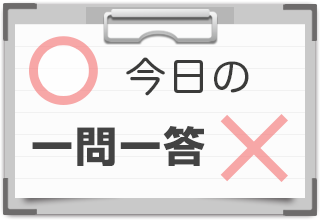第37回介護福祉士国家試験 問題の講評
第37回介護福祉士国家試験を振り返って
[後半:午後科目]
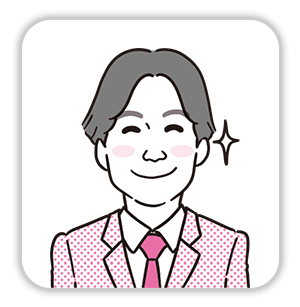
町田福祉保育専門学校 副校長
石岡周平(いしおか・しゅうへい)
町田福祉保育専門学校の石岡です。第37回介護福祉士国家試験を受験された皆様、お疲れさまでした。いまは自己採点も終わっているところでしょうか。前回に続きまして、今回は「午後」問題を振り返ります。今回受験した方、これから受験する方、各々の立場で参考にしてください。なお、解答案については、こちらをご覧ください(社会福祉振興・試験センターによる正式な解答の発表は3月24日の予定です)。
前回もふれましたが、「午後」の問題は生活支援技術やコミュニケーションなど普段の実務にもつながるような分野の科目が多く、得点を稼ぎやすいのではないでしょうか。そのため、午後は「取りこぼし」なく、効果的に得点を積み重ねることが重要なポイントとなります。そのコツなどにもふれながら、各科目を振り返ってみましょう。
介護の基本[10問]
この科目では、介護の成り立ちから現在に至るまでの歴史にはじまり、介護福祉士を規定する法律である「社会福祉士及び介護福祉士法」やその役割・倫理など、この資格の基礎を学びます。介護の対象となる人の理解や自立支援、介護サービスの理解、多職種連携、安全とリスクマネジメント、労働者としての法制度に健康管理など、内容は多岐にわたります。そのため、他科目と重なる部分が多いことも特徴で、介護についての学習を包括した学習範囲となっています。
国試では上記の項目からまんべんなく出題されますが、半分は法制度や理念などの知識が問われる問題、もう半分は利用者やその家族、介護従事者などの心情や対応方法などが出題となる傾向です。知識系は「社会の理解」と重なる部分も多いため、併せての学習となりますが、「心情や対応方法」に関する出題は得点を重ねたいところです。午後の科目ではこのような問題が多くなりますので、「自立支援」「利用者主体」「受容・共感・傾聴」「安全」という視点を、どの設問がより意識しているのか、できているのか。解答の際のポイントになるので覚えておくとよいでしょう。
第37回の特徴としては、法制度に関する問題が4問、「介護保険施設における防災対策」と「結核の予防対策」に関する出題がありました。こちらは難易度が高かったのではないでしょうか。「介護福祉職の対応方法」を問う短文事例2問は確実に得点したいところで、訪問介護員が行うサービス内容を含めて「利用者主体」「自立支援」などの基本姿勢をしっかりと意識できていれば解ける問題です。こちらは難易度としては低く、みなさんも得点できたのではないでしょうか。
法制度で例年出題される「社会福祉士及び介護福祉士法」は、その資格を取得する試験である以上、必ず得点したいところです。「介護保険施設における防災対策」は、近年さまざまな災害に見舞われており、各施設、事業所、介護従事者にとって他人事ではない項目です。試験対策というだけでなく、防災の法制度、災害時の避難や対応などさまざまな事柄を知っておくことで現場でも生かせるでしょう。今回は「結核の予防対策」が出題されましたが、こちらも近年さまざまな感染症が流行して介護現場ではその対応に苦労するところだと思います。「予防対策」「流行時の対応」などをしっかりと理解して「生命を守る仕事」だという意識を再認識したいですね。
コミュニケーション技術[6問]
介護は「人間が人間にする」ことから、人と接するときに必要となるコミュニケーションの基本や基礎的技術、さまざまな対象者への方法、チーム・コミュニケーション、記録の方法などについて学習する科目です。国試では以前は8問が出題されましたが、前回の第35回から「人間関係とコミュニケーション」が2問増えて4問となったことに伴って、「コミュニケーション技術」は2問減って6問となりました。昨年同様に、第37回でも全体の半分となる3問が短文事例問題となっていて、読解力も併せて求められる傾向です。
今回の短文事例問題は、介護の基本となる「利用者尊重」「受容・共感・傾聴」を意識していれば解けた問題で、「家族の意向」に関しても同様の視点で得点できたと思われます。例年出題されていた「技法」などの基礎的な分野からの出題は少なかったのが印象的です。そのため知識が問われず、難易度は低かったかもしれません。次回(第38回)は出ると考えて、技法などの基礎を重点的に学習するのも一つではないかと思います。
生活支援技術[26問]
この科目で学習する分野は、「生活支援(家事)」「生活支援技術(介護技術)」「福祉用具・住環境」の大きく3つに分けられます。生活支援(家事)では、家庭経営から掃除、調理、洗濯(被服)などを学びます。生活支援技術(介護技術)では、ADLに関する分野(移動、身じたく、食事、入浴、排泄、睡眠など)や終末期における介護技術を学んでいきます。福祉用具や住宅改修は、介護保険制度では購入や貸与の対象となっており、関連する分野を学びます。国試では、生活支援や福祉用具・住環境では知識を問われる出題がありますが、生活支援技術では「根拠に基づいた介護方法や留意点」「心情や対応方法」に関する出題が多い傾向です。
「介護方法や留意点」の出題は日頃の業務を根拠立てて考えることで対応でき、「心情や対応方法」の出題は先ほどふれたポイントで解答可能です。介護福祉士を受験する人にとって、全科目の中で一番身近な科目であるために難易度は全体的には高くないと思うのですが、毎年数問、「高難度」であったり、「驚いた!」というような印象に残る問題があります。今回は特にそのような問題はなく、出題がおとなしめだった印象です。唯一印象に残ったのは、問題105でした。脳性麻痺(アテトーゼ型)の利用者が使用する「情報・意思疎通支援用具」として、福祉電話や携帯用会話補助装置、助聴器などは知らない人も多かったのではないかと思います。
全体的に過去出題の問題に類似した基礎的な技術から出題されていて、難易度は高くなかった印象です。近年「家事支援」に関する問題が3~4問程度、必ず出題されています。第37回は「基本調味料の効果や使い方」「食品の保存」「衣類の保管方法」が出題されました。このあたりは普段から自宅で家事をしている人や訪問介護員では基本となる項目で正答しやすかったでしょう。普段家事をしない人や養成校ルートの新卒学生などは、重点的に学習が必要かもしれません。例えば、今回の問題を解くカギになる調味料の「さ・し・す・せ・そ」や「消費期限と賞味期限」などは覚えておくと日常生活で役立つものです。
全科目中、一番出題数が多い「26問」となるため、この科目で安定的に多くの得点を稼ぎたいところです。
介護過程[8問]
介護とは、対象者への「よりよい生活の提供」が目的になるといえます。よりよい生活を提供するためには、その対象者を知り(アセスメント)、その方法を考え(計画)、実際に支援(実践)し、その結果を反省(評価)する必要があります。各事業所などに勤務されている皆様も日々の業務でこのようなことを常に頭の中で考えているはずなのです。それを学問にしているのが「介護過程」といえます。国試では、「意義や基礎的理解」「チームアプローチ」「展開の理解」(さまざまな事例の検討)という項目から出題されます。
介護過程でも、短文事例問題が1問と一事例2問で2事例計4問が出題されています。科目の特性か、半数以上が事例となるので、ここでも読解力が求められます。前半の出題は、例年「アセスメント」「計画立案」「目標設定」「評価」といった介護過程の基礎となる項目から出題されます。この科目の中では学習しやすい項目なので、しっかりと押さえておく必要があります。事例問題では、その学習が役に立ちます。さらに「介護福祉職が何をするか」という視点ではなく、「利用者にとって何が必要なのか」という視点が、得点するためには重要になります。
毎年難易度は低めの科目ですが、第37回でも多く得点ができたのではないでしょうか。
総合問題[12問]
「高齢者(2事例)」「障害者(2事例)」の4事例、各事例に3問ずつ出題がある合計12問が総合問題となります。出題内容は「関連する法制度」「対象者の疾患名や特徴」「対応方法」などが問われ、事例を読解して解答を導きます。そのため、全科目をしっかりと学習しておくことが必要です。そのうえで、模試や模擬問題集などで傾向や読解力を養うとよいでしょう。
第37回の総合問題では、過去に実績のない「ジェノグラム」がイラスト問題で出題されました。これは介護過程で学習する分野で、情報収集の際に使用するものです。もう一つ特徴的だったのが、「人間の尊厳と自立」科目で過去に出題例がある福祉や介護にかかわる思想などを確立した人物に関する問題です。着替えで疲れてしまう利用者を「着替えは家族や介護を利用して、好きな絵が描けるようにする」という自立支援を大切にしながらも自己実現を図る「自立観」を示した人物が問われました。「人間の尊厳と自立」「障害の理解」などで学ぶ、1960年代にアメリカで起こった、障害者による「IL運動」時代の人物「エド・ロバーツ」です。この人が上記の「自立観」を提唱した人でした。総合問題で、このような出題がされるのは驚きでした。
さて、2回に分けて第37回介護福祉士国家試験を振り返っていきました。以前は「筆記試験と現場は違う」ととらえられていたように思いますが、そんなことはありません。介護現場に役立ち、よい介護ができるように国家試験があり、学習する内容はそこをとらえたものになっているのです。
日々の勤務をしながら学習することは大変で、努力が必要になります。ですが、そこで学習したことは必ず業務に生きます。頑張って国家試験に挑戦して合格し、取得した「資格証」は誇るべきものです。努力した自分を褒めるためにも喜ぶべき証です。よく「職場で言われたので資格を取らなくては」と嫌々受験をしている方の声をよく聞きます。しかし、資格はその取得するための「過程」にこそ意味があると思います。学習することは、介護現場での業務への自信になり、きっとよい介護につながるでしょう。
これから受験をめざす方は、日々の学習は大変なことだろうと思います。「過程」を大事にしながら努力を続け、自信をもって来年の国試受験に挑戦できるようになることが、ある意味では資格証よりも大切なことかもしれません。頑張ってください。
- ・「人間の尊厳と自立」(2問)+「介護の基本」(10問)で、1科目群
- ・「人間関係とコミュニケーション」(4問)+「コミュニケーション技術」(6問)で、1科目群
- ※全11科目群の各科目群で1点以上の得点がないと、総合得点が合格点に達していても不合格となる。