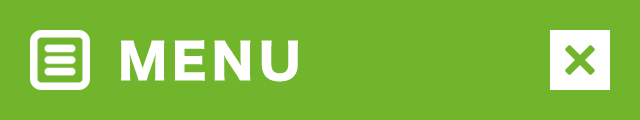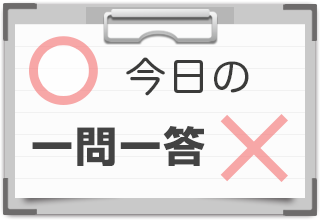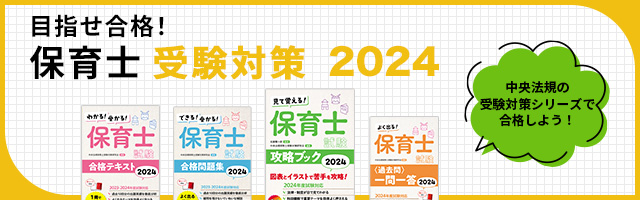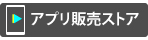受験対策講座
保育士・筆記試験の合格率は20%前後で難関といえます。この狭き門を突破するためには、ポイントを押さえた効率のいい学習が不可欠です。このコーナーでは、近年の各科目の出題傾向や今後の対策について、その秘訣をガイドします。
※毎週火曜日更新!
2025年4月試験に向けた講座がスタートしました!
第58回 令和6年後期・保育士試験「教育原理」の内容や難易度は? 傾向と対策のポイント

綾 牧子(あや まきこ)
学研アカデミー保育士養成コース専任講師、文教大学非常勤講師、国家資格キャリアコンサルタント
令和6年度後期試験の出題傾向
① 教育基本法・学校教育法
令和6年後期試験では、教育基本法や学校教育法について問われました(問1・4)。
特に、教育基本法は教育関係の最も重要な法律です。第1条(教育の目的)・第2条(教育の目標)は、条文もしっかりと読み込んでおいてください。
② 幼稚園教育要領
令和6年後期試験では、幼稚園教育要領の中から、第3章「教育課程に係る教育時間の修了後等に行う教育活動などの留意事項」に関する正誤が出題されました(問6)。
「教育課程に係る教育時間の修了後等に行う教育活動」とは、いわゆる「預かり保育」です。幼稚園では、「教育課程に係る教育時間」(標準4時間)と別に教育活動計画を作成することとされています。
③ 西洋及び日本の人物と思想
教育・保育の歴史上で重要な「人名」「有名な著書」「理論」の内容が毎回出題されます。
令和6年後期試験では、日本の人物として森有礼が出題されました(問3)。森有礼が初代文部大臣であることは、日本教育制度上で最重要事項です。
西洋の人物・思想では、フレーベルについて出題されました(問5)。ルソーやモンテッソーリについても理解しておくと正解しやすい問題でした。
④ 教育制度及び教育行政
・戦後の教育改革
令和6年後期試験では、戦後の教育改革に関して教育基本法や学校教育法、教育委員会法の内容が問われました(問4)。
現在の教育制度の基本(男女共学、9年の義務教育、6・3・3・4制、教育委員会制度など)は、戦後の教育改革によって形作られました。
・教育振興基本計画
令和6年後期試験では、教育振興基本計画が出題されました(問7)。
教育振興基本計画は5年おきに策定されており、現在は第4期(2023~2027年度)となっています。計画のコンセプトをおさえておきましょう。
⑤ 教育を取り巻く諸問題
・リカレント教育
令和6年後期試験では、リカレント教育について問われました(問8)。
リカレント教育はOECD(経済開発協力機構)から提唱された概念で、「必要に応じていつでも教育機関に回帰することのできる教育」のことを指します。
・いじめ防止対策推進法
いじめ防止対策推進法の第8条(学校及び学校の教職員の責務)の穴埋め問題が出題されました(問9)。
児童相談所等の関係機関と連携すること、学校全体として未然防止と早期発見が重要であることをおさえておきましょう。
今後の受験対策、勉強の進め方
令和6年後期試験では、西洋教育史と幼稚園教育要領に関する問題で「適切なものを3つ選びなさい」という形の出題が見られました。正確に正誤を判断する力が問われます。
テキストでポイントを確認し、過去問で理解を定着させる学習を繰り返しましょう。
① 教育の意義・目的と教育法規
法令に関する問題は毎回必ず出題されます。特に、憲法・教育基本法・学校教育法は頻出です。テキストで出題されやすい条文を確認してください。
その他、児童福祉法や子ども・子育て支援法等、福祉分野の法令も出題されることがありますが、教育と関係がある条文が出題されやすいです。
② 幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針
幼稚園教育要領の「第1章 総則」は出題されやすい部分です。
なお、近年は幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針において、整合性の図られた部分の出題が多く見られます。詳しくは合格テキストで確認してください。
幼保連携型認定こども園教育・保育要領については、「幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項」についても確認しておきましょう。
③ 教育の思想と歴史的変遷(西洋及び日本の人物と思想)
「人名・国名」「有名な著書」「理論」を結び付けて理解してください。
合格テキストに掲載されている一覧表を参照し、自分なりにノートや単語帳に整理しておきましょう。
近年は、その人物の教育思想を理解していないと正解できない問題も多く見られます。
有名な著書の内容から、著者の教育思想について理解を深めましょう。
特徴的な教育実践の方法は、現代にまで息づいているものも多くあります。
④ 子どもの権利と保護
子どもの権利については、国際的な動きと日本の動きの双方を意識しながら学習すると、流れをつかみやすいです。
「児童憲章」「児童権利宣言」「児童の権利に関する条約」「こども基本法」が制定されてきた歴史的変遷を合格テキストで確認してください。特に、2023(令和5)年4月に施行されたこども基本法は要確認です。
人権教育や家庭教育支援、児童虐待防止といった具体的な教育施策から「子どもの権利」を捉えることも大切です。
⑤ 教育制度及び教育行政
・戦前から戦後の教育制度
戦前から戦後の教育制度の流れについては、合格テキストを参考に重要事項を年表で確認してください。
日本の学校教育制度の始まりである明治初期から大正時代、そして戦前から戦後までの教育制度のおおまかな流れについておさえておくことが必要です。
・国の教育政策
中央教育審議会の答申や報告書からの出題が多くなっています。
文部科学省のホームページ等で閲覧できるので、過去問で出題された答申等の概要を確認しておきましょう。
また、保幼小接続に関する出題も見られます。
幼稚園教育要領と小学校学習指導要領とが関連している部分(「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」など)は要確認です。
・諸外国の教育制度と教育実践
近年の特徴的な教育・保育実践に関する出題が多いです。「名称」「実践を提唱した人名と国名」をセットで確認してください。
合格テキストに掲載されている一覧表を参照し、自分なりに整理しておきましょう。
特に、「レッジョ・エミリア・アプローチ」「テ・ファリキ」「イエナ・プラン」などの保育実践は理解を深めておきたいところです。
また、諸外国の教育制度についても出題されることがあります。諸外国の学校の種類や教育政策を確認してください。
⑥ 教育を取り巻く諸問題
国際的な動向や日本国内の教育問題について、日頃から関心を持っておくことが大切です。キーワードをテキストで確認し、内容を理解しておきましょう。
ESDやSDGs、OECDの学習到達度調査(PISA)、生涯学習社会に関連するキーワード(成人教育論、リカレント教育など)、子どもの自殺やいじめの状況と対策、特別支援学校、GIGAスクール構想などは内容を理解しておきたいところです。
もっと問題を解きたい人は合格アプリ!
保育士 合格アプリ2025
一問一答+穴埋め
『よく出る!保育士試験<過去問>一問一答2025』のアプリ版!
保育士試験10回分から頻出問題1,456問を収載。繰り返しの学習に最適です。
- 詳細はこちらから
- ダウンロードはこちらから


- ※この商品は、スマートフォンとタブレットでご利用いただけます。パソコンでは操作できません。
- 受験対策図書の情報はこちら!
受験対策コンテンツによりアクセスしやすい! けあサポ・アプリ版
けあサポ ―介護・福祉の応援アプリ―
- ※ 上記リンクから閲覧端末のOSを自動的に判別し、App StoreもしくはGoogle playへと移動し、ダウンロードが可能です。