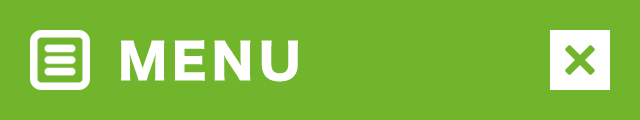子どもと表現 応答性豊かな保育者になるために
内容紹介
本書は保育士養成および幼稚園教諭養成のテキストで、幼児と表現など、保育内容の「表現」活動に焦点を当てています。
コアカリキュラム「領域に関する専門的事項」の考え方に示されているように、本書では領域表現の学問的な背景や基盤となる考え方を学ぶことを基本とします。幼児教育・保育で、子どもに「何をどのように指導するのか」の「何を」について焦点をあて、各章を構成しているのが特徴です。
本書の特徴
- ●類書の多くは「保育内容表現」として、主に子どもの表現活動を指導するために「どのように指導するのか」が中心であり、各大学の授業では「何を」については、保育者養成課程の科目担当教員の専門性に委ねる場合が多いことが予想されます。子どもの表現は「造形表現」「音楽表現」「身体表現」等と区分されていません。しかし、子どもの「表現(表出)」の特性を見極め、保育者が子どもの表現がさらに広がるようかかわろうとするとき、その子どもの「表現」に応じた「造形表現」「音楽表現」「身体表現」のいずれかに寄せたアプローチをすることも大切です。そのためには、保育者養成校の学生が、子どもの表現と発達を理解し、「どのように指導するのか」につなげることができるよう、専門的事項について理解する必要があるのです。
- ●1つのテーマ(章)について、子どもに「何をどのように指導するのか」の「何を」を主軸に置くことで、幼稚園教育要領等のねらい及び内容を基本としながらも、保育者養成課程の科目担当者の専門性(造形・音楽・身体)が活かされるよう、一方で専門性が補えるように構成されています。
- 本書をとおして子どもの表現(区分されていない総合的な表現、融合された表現)を理解するとともに、「造形表現」「音楽表現」「身体表現」それぞれの視点から学ぶことで、さらに子どもの表現が広がるための知識・技能・表現力等を身につけることを目指します。
編集者から読者へのメッセージ
「こどもまんなか型」表現のテキスト
表現活動に関する類書が数多く発行されている中で、本書はどのような特徴があるのか……。その答えは「序章」にあります。
表現方法に主眼を置くテキストが多い中、本書は「何を教えるのか」に力点を置いています。いわば「目的」重視型のテキストです。目的が明確になれば、「どのように教えるか」という「手段」は場面に応じて選択することができます。子どもの姿に合わせて可変的に手段を選ぶ目を養うことができるのです。
主な目次
序章 子どもの表現を育むために
第1部 表現の芽生えと出会い
第1章 豊かな表現と感性を育む
第2章 子どもの素朴な表現との出会い―発達のプロセス
第2部 応答性豊かな保育者になるために
第3章 自分との応答―自分自身の表現を感じる・みる・聴く・楽しむ
第4章 素材との応答―ものの特性を活かした表現
第5章 他者との協働―人と協働し合う表現
第6章 環境との応答-空間・場と相互作用した表現
第7章 文化との出会い―児童文化財、伝承遊び、行事にみる表現
第8章 ICT(情報機器)との出会い―表現の多様性を知る
著者情報
編著者
島田由紀子 國學院大學教授
駒久美子 千葉大学准教授
著者
駒久美子
島田由紀子
小笠原大輔 湖北短期大学准教授
山辺未希 横浜国立大学助教
大塚習平 東京都市大学教授
中村昭彦 淑徳大学准教授
井上昌樹 育英短期大学講師
馬場千晶 昭和学院短期大学助教
仲条幸一 つくば国際短期大学講師