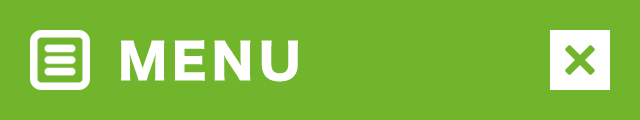これまでの枠を超えれば「ワクワク」がみえてくる
空間・時間・人を拡げる 保育環境の構成
内容紹介
保育において、環境を考えることは基本中の基本です。しかし、無意識のうちにさまざまな「枠」に囚われ、実践が行き詰まる、園生活に切れ目が生じる、資源や人材が活かされないということも多いのではないかと思います。
本書は、そうした「枠」を逆手に取り、子どもも大人ももっとワクワクできる保育を創造するためのアイデアブックです。これまで注目されてこなかった空間や時間の魅力を活かした実践、職員の多様な働き方や活躍の仕方を創出する試み、地域やそこに暮らす人々とより豊かな関係構築を目指した取り組みなど、全18 事例を紹介します。
事例提供園
幼保連携型認定こども園清心幼稚園(群馬県前橋市)
幼稚園型認定こども園武庫愛の園幼稚園および幼稚園型認定こども園立花愛の園幼稚園(兵庫県尼崎市)
編集者から読者へのメッセージ
著者の境愛一郎先生は、日ごろからフィールド活動として、清心幼稚園や愛の園幼稚園にかかわっています。その研究はこれまで、保育に関する学会などで発表されてきました。
境先生らの研究のユニークな点は、環境を従来の枠の中だけでとらえないことです。今回ご紹介する18の事例をみても、空間の枠はもとより、人の役割という枠、時間という枠を状況に合わせて考え変えている様子がわかると思います。
皆さんの園でも枠を広げてみると、子どもの「ワクワク」が見えてくるのではないでしょうか。
主な目次
序章●これまでの保育環境を問い直してみよう
第1 章 空間から環境の構成を考える
1 「仕切り」がつくる新たな環境—限られた空間を活かしながら
2 世界観を投影して遊ぶ保育空間
3 園と地域とを行き来する面白さ—園の内側と外側という「枠」を超えて
4 園生活を充実させる通園バスのあり方
5 大人たちの場を考える—休憩室が完成するプロセス
6 イマジネーションとリアリティの境界を遊ぶ—「〜かも」を面白がりながら
第2 章 時間から環境の構成を考える
7 子どもがワクワクするおやつ時間
8 落ち着く、気を抜く、解放する夕方の保育
9 平日にはできないことを可能にする「土曜保育」
10 行事はゴールではなくスタートの日!? ー時の流れを切らない試行錯誤
11 年度替わりの時間的環境を見直そう—「区切り」から「移行」へ
12 素材も遊びもとっておこう! 「ディスプレイ」で続きを楽しむ
第3 章 人から環境の構成を考える
13 保育者の姿を「見せる」ことで「魅せる」保育環境
14 調理員、用務員が子どもにもたらす豊かな経験
15 保護者と園のコラボレーション
16 アーティストと園が相互成長する関係性
17 地域の専門店とつくる「食」を通じたかかわり
終章 これからの保育環境を創造しよう
18 保育環境における「色」を考える
著者情報
編著者 境愛一郎(さかい・あいいちろう)
共立女子大学家政学部准教授、博士(教育学)。宮城学院女子大学助教を経て現職。著書に『保育環境における「境の場所」』(ナカニシヤ出版、2018 年)、『質的アプローチが拓く「協働型」園内研修をデザインする:保育者が育ち合うツールとしてのKJ法とTEM』(ミネルヴァ書房、2018 年)がある。
著者 栗原啓祥(くりはら・ひろあき)
認定こども園清心幼稚園(群馬県前橋市) 副園長。修士(教育学)。青山学院大学大学院教育人間科学研究科で学び、現在は、子どもが思いや想像を発揮し、さまざまなかかわりを通して創出する実践と環境を探求している。
著者 濱名潔(はまな・きよし)
認定こども園武庫愛の園幼稚園 法人本部 副本部長、博士(教育学)。保育現場での実践と理論の融合を目指し、園内研修のデザインや保育者の専門性向上に関する研究も行っている。
-
これまでの枠を超えれば「ワクワク」がみえてくる
空間・時間・人を拡げる 保育環境の構成判型:AB
頁数:132頁
価格:2,420円(税込)
発行日:2025/3/1