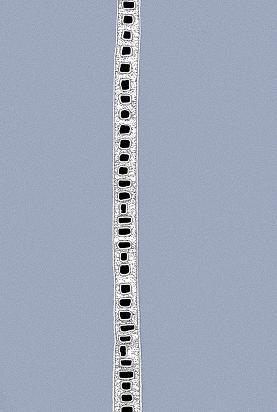2010年01月
2010年01月
手紙を入れたガラスびん
「母からの手紙」
誰かと言い争ったとき、誰かの言葉に傷ついたとき、誰かを傷つけてしまったのではと不安な夜、私は認知症の母へ手紙を書く。返事の来ない手紙を書く。ただいつものようにお元気ですかで始まり、寂しくないかと付け加え、元気でねと母へ手紙を書く。言葉のない母は、手紙を読みもしないで、口にくわえてしゃぶると聞いた。
補い合うこと
この手の長さ
背中のあたりがかゆくて苦しんでいると
「一人では
何でもかんでもできないように
手はちょうどいい長さに作ってあるのよ」と母は言って
ぼくの背中の手の届かないあたりを
かいてくれた
そんなに言っていた母も認知症になり
母一人では何にもできなくなった
母一人では渡れない川を
二人で渡りきろう
母一人では登れない山を
二人で越えよう
人が孤独にならないように
人が愛で引き合うように
人が人を必要とするように
人が傲慢にならないように
この手をこのちょうど良い長さに
作ってあるに違いない
ぼくにもとうてい一人では
できないことがある
できない二つのことが
母とぼくとで
できる二つのことになる日が
来るのかもしれない
ぼくの人生の地図の一部が
母の中にあり
母の人生の地図の一部が
ぼくの中に
きっと潜んでいるに違いない
『やわらかなまっすぐ』(PHP刊)に関連文
私たちがかえる場所
「捨てる」
ある日
突然
母が車の窓からゴミを捨てた
ティッシュが花びらのように
車から遠ざかる
セロファンが春の光に
キラキラと光って
私たちから遠ざかっていった
後続の車の人から怒鳴られた
事情を話し、頭を下げた
母がその大きな怒鳴り声を聞いて
笑うものだから
怒鳴り声がさらに大きくなる
母の笑い声はいつもよりまして
高らかだった
母は言葉を捨てた
母は女を捨てた
母は母であることを捨てた
母は妻であることを捨てた
母はみえを捨てた
母は父を捨てた
母は過去を捨てた
母は私を捨てた
母はすべてを捨て去った
そして一つの命になった
でも私には
母は母のままであった
母が認知症という病気を脱ぎ捨て
生きることを捨てて
あの世への階段を上る時
太陽の光を浴びて
命は輝き
あの時のセロファンのように
私から遠ざかっていくのだろうか
詩集「手をつないで見上げた空は」
海と母、そして私
「母に会うときは」
朝に母に会うときは
「おはようございます」と言う。
昼に会うときは
「こんにちは」と言い
夜には
「こんばんは」と頭を下げ
寝るときには
「お休みなさい」を忘れない。
正月には
「あけましておめでとうございます」
と正座して母に向かい合い。
認知症の母は食事はしないけれど
母の箸を用意し
縁起の良さそうな袋に入れて
母の前に置く。
母の雑煮。
母にお屠蘇。
言葉がないから
母に心がないわけではない。
何も分からないから
何もしないで良いとは思わない。
何を言っても理解できないから
何を言っても許されるというものでもない。
母の存在が私の良心を見つめている。
母が叱りつけるような厳しい目で
私を見つめるときがある。
母という海に自分自身の姿を
しっかりと映しながら
私は自らを確かめる。
母はベッドに横たわり
私を育て続ける。