
ラムネの喜び
『ラムネ』
母はラムネの栓を
ポンと要領よく抜いて
泡が吹き出すラムネの瓶を
手渡してくれた。
知識をいっぱい身につけて
いっぱい覚えておくと
大人になってから
いいことがある
と言っていたのは母だった。
アルツハイマー‐びょう【―病】‥ビヤウ
老年痴呆の一型。初老期に始まり、記銘力の減退、知能の低下、高等な感情の鈍麻、欲望の自制不全、気分の異常、被害妄想、関係妄想などがあって、やがて高度の痴呆に陥り、全身衰弱で死亡する。脳に広範な萎縮と特異な変性が見られる。ドイツの神経病学者アルツハイマー(A.Alzheimer 1864-1915)がはじめて報告。
知識から
生まれてくるのは
不安だけじゃないか。
何の役にもたちゃしないぞ
母さん
知識なんて。
ラムネを飲み干して
空(から)になったラムネの瓶を
すかして空(そら)を見た。
「お母さん、瓶に青い空(そら)が入ったよ」
と、幼い私は言った。
今、記憶も何も入っていない
空っぽの母をすかして
この私がしっかりと見えている。
瓶の色で微妙に変わった
幼いときの空の青色を思い出す。
※引用は『広辞苑第四版』
詩・イラスト=藤川幸之助
幼い頃、夏にはよくラムネを飲んだ。ラムネの栓を開けるのは幼い子どもでは無理だと、必ず大人がラムネ専用の栓あけでラムネのふたになっているビー玉を中に押し入れてくれた。ポンという音とともにシュワーという炭酸の音。幼い私は、飲み口からあふれているラムネがもったいないと思っていた。少々重くて厚手の瓶であったので、両手でしっかりと握って飲んだのを憶えている。ラムネを飲むとき、瓶のくぼみにうまくそのビー玉を引っかけて飲まないと、なかなか中のラムネは飲めないのだ。要領の悪い私は、ビー玉をなかなかくぼみに引っかけられず、中のビー玉が飲み口をすぐにふさいで、ラムネを全部飲んでしまうのに時間がかかった。とにかく、中に入っているビー玉が邪魔で邪魔でしかたなかった。
母の介護を始めた頃は、不安だらけだった。母はこれからどうなるのだろう。母の死を考えると、いたたまれなくなった。私はこれからどうなるのだろう。おしめもうまく替えられない。食事も上手に食べさせることができない。何をやってもうまくいかない。自分のイメージ通りに動かない母に、いつも苛ついてもいた。母の病が、私の未来に壁のように立ちはだかっていた。ラムネの瓶の中のビー玉のように邪魔で邪魔でしょうがなかった。そう思って、認知症という「病」のことばかり考えていたからだろうか、認知症に関する本を何冊も何冊も読んだ。認知症のことをやっているテレビも全て録画して見た。その中に、答えがあるような気がして、繰り返し読み、何度も何度も見た。でも、答えはその中にはなかった。詩の中の「知識から/生まれてくるのは/不安だけじゃないか。/何の役にもたちゃしないぞ母さん/知識なんて。」と思っていたのもその頃。
その頃、私は小学校で教員をしていた。授業の中で子どもができないことや教室の内外で日々起こる子どもの問題に手を焼いていた。何をやってもうまくいかない。自分のイメージ通りに動かない子ども達に、いつも苛ついていた。子どもの問題もまた、ラムネの瓶の中のビー玉のように邪魔で邪魔でしょうがなかった。その問題を排除することばかりを考えていた。授業のやり方や問題行動への対処の仕方の本を何冊も何冊も読んだ。母の認知症を考える時と同じように、子ども達の問題や「できないこと」にばかり目がいっていた。ある日、昼休み、子ども達の無邪気に遊ぶ姿を見た。子ども達の動きは伸びやかだった。子ども達の顔は輝いていた。子ども達の問題行動にばかり目がいき、この子ども達を「見つめること」を忘れていたと、私は思ったのだ。
その帰り、母の病院へ行った。病気や方法、技術にばかり目がいって、母そのものを私は忘れているのではないかと思った。それから、「病」ではなく、「母」そのものをしっかり見つめるようになった。そうしている内に、認知症なんて老いの一つの形でしかないと思えるようになった。母が老い、死へ向かっていく。それを息子の私が支える。至極当たり前のことを、私はしているだけなのだ。そう思ってから母の認知症自体も邪魔だとは思わなくなった。知識も、私にとっては母のために役立てるものになった。母を見つめ、母を感じることがどれほど大事か、そこから方法は幾通りも生まれてきた。そこに答えはいくつも見つかった。
私はビー玉をなかなかくぼみに引っかけられず、ラムネを全部飲んでしまうのにとにかく時間がかかった。しかし、今思えば、瓶を回したり、傾けたりしながら、その邪魔なビー玉をくぼみに引っかけようとすること自体がとても楽しかったような気がする。その楽しさやできる喜びがあったから、飲みにくいのに何度も何度もラムネを飲んだのかもしれない。母の介護もそうだ、邪魔だ邪魔だとか、もう嫌だ嫌だとか思いながらも今まで続けてこれたのは、そこに喜びがあったからかもしれない。その時には、いたたまれなかった時もあったが、今思うと知らぬ間に喜びや充実感を感じていたように思う。母の介護も人生も、邪魔だと感じることや抵抗があるからこそ、楽しいのだ。楽しいとまで思わないまでも、充実しているのだ。それを避けて、そこから私が逃げていたら、私の人生には充実感や喜びも少なかったと思う。邪魔だ邪魔だと思いドタバタしながらも、自らの人生を引き受けて生きてきた。そうしている内に、自らの人生の答えがふと明確に見えるときがあった。それこそ、喜びであり、幸せであるような気がするのだ。
◆SAKさん、コメントありがとうございます。「何も持たない自分でも、宿命を全うしようとする事で
自分の色を増し、気付くと周りの人たちが自分を囲み、支え、助けてくれる。」とSAKさん。私は自分の
詩の解説を書くのはあまりしません。読み手の想像力を削いでしまうかもしれないと思うからです。
ですから、自分の詩は自分の手から離れたらどのように読まれてもいいと思っています。でも、SAKさんの私の詩へのコメントを読むと、詩を書いていてよかったと思います。自分の思いがしっかりと伝わっている気がするからです。SAKさんとは、もしかすると詩人の萩原朔太郎さんではありませんか?そんなわけはないですよね。

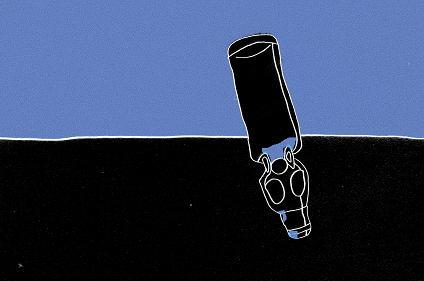










コメント
『ラムネ』、切なくなりました。
知る事で得られる喜びもあれば、落胆する事もある。
僕も初めて母の認知症を知った時は
『母の介護をどうしよう。』
『認知症の母を持った自分の今後はどうなる。』
といった、自己中心的な考えでその当時は日々を過ごしていました。
そんなある日、母が発症してしまった経緯を考えてみた時、それまで自分がどれだけ母の生活に無関心であったか。そして母の心労をなぜ一緒に暮らしていた自分が察して、助けてあげる事ができなかったのか。
と、後悔の念に襲われてしまいました。
発症した経緯はあくまでも僕の憶測に過ぎないのかもしれませんが、ある時から母と向き合わなくなっていた事は動かざる事実として自覚する事ができました。
自覚した日から数年経ちましたが、今はできる限り母と向き合い、もっともっと母の事を知りたいと思っています。
きっと母の事を今以上に知る事で、認知症を知った時の不安を忘れるくらいの喜びが待っているのかもしれないと、そんな勇気を今回はいただきました。
知識は道具のひとつにしか過ぎないと思っています。
その道具も使う人の心の有り様で育むものにも傷つけるものにもなり得る。
認知症の母だけに限らず、自分を取りまく沢山の方たちに対しても、僕が得る知識という道具が役に立てばいいなと改めて思いました。
※コメントはブログ管理者の承認制です。他の文献や発言などから引用する場合は、引用元を必ず明記してください。なお頂いたコメントは、書籍発行の際に掲載させていただく場合があります。